日本共産党横浜市会議員
古谷やすひこブログ
市内にある米軍基地内でどこに危険物があるかが分からず消火活動を強いられるのか!! ~横浜市会決算特別委員会・消防局審査(10月5日) その二
市内米軍基地内での火災対応に向けて最大限の努力を
古谷議員: 次に、相模総合補給廠での火災に関して市内米軍基地内での火災の対応について、伺ってまいります。 8月24日に起こった相模原市の米軍施設・相模総合補給廠の爆発火災に関連して、新聞報道の中では、相模総合補給廠の中には日本の消防法上の危険物施設が16あるといった報道が流れました。本市の米軍基地内に、消防法上の危険物施設、どこにいくつあるのか、本市として把握されているのか、伺います。  久保田消防局長: いわゆる日米地位協定において米軍が管理している施設内の詳細を把握することは困難でございます。ただし、毎年米軍との合同訓練を実施する中で、消防法上の危険物質については、鶴見貯油施設に屋外貯蔵タンク20基があることなどは把握しております。
久保田消防局長: いわゆる日米地位協定において米軍が管理している施設内の詳細を把握することは困難でございます。ただし、毎年米軍との合同訓練を実施する中で、消防法上の危険物質については、鶴見貯油施設に屋外貯蔵タンク20基があることなどは把握しております。  古谷議員: 一般的にですが、火災の状況あるいは火元が何かとか、そういう状況を確認せずに、消防として出動することはあるのでしょうか。 高坂警防部長: 火災の通報を受けた際には、何が燃えているのか必ず確認いたします。通報内容から建物、車両など燃えているものや場所を特定して、対応する出動警報によりまして、消防隊等を選別して出動させるところです。 古谷議員: だとしたら、基地内でもし火災が起こった場合、米軍からの要請を受けて本市の消防が出動した際に、火災の状況が危険物なのか危険物でないのかなど把握すること、ぜひ必要だというふうに思うんですが、どうか伺います。 久保田消防局長: 出動した消防隊員は、施設の入り口またはその付近で必ず集結しまして、必ず米軍関係者から火災の状況や危険物の有無、保管状況などの情報を聴取し、消火活動の方針をしっかりと協議した上で、活動にあたります。 古谷議員: その問題と、また消火した後の問題もあると思うんです。消化した後も、基地内の火災の再発防止であるとか原因究明についても、相模原では1回やったということで随分新聞に大きく載りましたが、その後やられていないようですが、合同でやるべきだというふうに思いますが、どうか伺います。 久保田消防局長: いわゆる日米地位協定上の課題はありますが、災害発生時には、先般の相模総合補給廠での火災の対応などを踏まえて、再発防止や原因究明について、連携・協力できるよう、米軍にしっかりと申し入れをしてまいりたいと考えております。 古谷議員: ぜひ、本市の消防署員が危険な目に合わないように、最大限の努力をぜひ図っていただきたいというふうに思うんです。 本市と在日米軍との間で結んでいる消防相互援助協約、これによれば、要請を受けて基地内で消火活動中、もし不幸なことに負傷もしくは死亡しても請求権は放棄するというふうな取り決めになっているようです。もしそういった事態になれは、本当に隊員も報われないというふうに思います。 本市としても、神奈川県基地関係県市連絡協議会でも、地位協定についてはさまざまな改善の要望をされているというのは十々承知しています。それにとどまらず、ぜひ日頃から訓練などで一緒にしているというのであれば、本市と米軍との間で危険物に関する情報提供の仕組みを設ける必要があるというふうに思いますが、これは副市長に伺います。 柏崎副市長: 先ほど消防局からもご答弁しましたように、現段階ではいわゆる日米地位協定によりまして、事前の危険物貯蔵などの詳細な情報を得ることは困難というふうに考えております。しかしながら、本市で米軍施設の火災が発生し、市民のみなさまに影響を及ぼす恐れがある場合には、危険物などの必要な情報を速やかに提供するよう米軍に対して強く要請してまいります。 古谷議員: ぜひ、本市の消防隊員の安全、確保するためにも、ぜひ進めていただきたいと思うんです。さらには、日米地位協定の改善、早期の市内米軍基地の返還、ぜひ求めていきたいというふうに思います。
古谷議員: 一般的にですが、火災の状況あるいは火元が何かとか、そういう状況を確認せずに、消防として出動することはあるのでしょうか。 高坂警防部長: 火災の通報を受けた際には、何が燃えているのか必ず確認いたします。通報内容から建物、車両など燃えているものや場所を特定して、対応する出動警報によりまして、消防隊等を選別して出動させるところです。 古谷議員: だとしたら、基地内でもし火災が起こった場合、米軍からの要請を受けて本市の消防が出動した際に、火災の状況が危険物なのか危険物でないのかなど把握すること、ぜひ必要だというふうに思うんですが、どうか伺います。 久保田消防局長: 出動した消防隊員は、施設の入り口またはその付近で必ず集結しまして、必ず米軍関係者から火災の状況や危険物の有無、保管状況などの情報を聴取し、消火活動の方針をしっかりと協議した上で、活動にあたります。 古谷議員: その問題と、また消火した後の問題もあると思うんです。消化した後も、基地内の火災の再発防止であるとか原因究明についても、相模原では1回やったということで随分新聞に大きく載りましたが、その後やられていないようですが、合同でやるべきだというふうに思いますが、どうか伺います。 久保田消防局長: いわゆる日米地位協定上の課題はありますが、災害発生時には、先般の相模総合補給廠での火災の対応などを踏まえて、再発防止や原因究明について、連携・協力できるよう、米軍にしっかりと申し入れをしてまいりたいと考えております。 古谷議員: ぜひ、本市の消防署員が危険な目に合わないように、最大限の努力をぜひ図っていただきたいというふうに思うんです。 本市と在日米軍との間で結んでいる消防相互援助協約、これによれば、要請を受けて基地内で消火活動中、もし不幸なことに負傷もしくは死亡しても請求権は放棄するというふうな取り決めになっているようです。もしそういった事態になれは、本当に隊員も報われないというふうに思います。 本市としても、神奈川県基地関係県市連絡協議会でも、地位協定についてはさまざまな改善の要望をされているというのは十々承知しています。それにとどまらず、ぜひ日頃から訓練などで一緒にしているというのであれば、本市と米軍との間で危険物に関する情報提供の仕組みを設ける必要があるというふうに思いますが、これは副市長に伺います。 柏崎副市長: 先ほど消防局からもご答弁しましたように、現段階ではいわゆる日米地位協定によりまして、事前の危険物貯蔵などの詳細な情報を得ることは困難というふうに考えております。しかしながら、本市で米軍施設の火災が発生し、市民のみなさまに影響を及ぼす恐れがある場合には、危険物などの必要な情報を速やかに提供するよう米軍に対して強く要請してまいります。 古谷議員: ぜひ、本市の消防隊員の安全、確保するためにも、ぜひ進めていただきたいと思うんです。さらには、日米地位協定の改善、早期の市内米軍基地の返還、ぜひ求めていきたいというふうに思います。
議会への当局説明が不正確では、二元代表制が成り立たない!! ~横浜市会決算特別委員会・消防局審査(10月5日) その一
議会での局長答弁は正確でないと二元代表制なりたたず
古谷議員:
日本共産党、古谷やすひこです。
まずはじめに、アルコール検知器の使用状況をめぐって、常任委員会での不正確な説明がなされたことについて、少し伺ってまいります。本来は、この質問がしなくてもいい事態を望みますし、わが党としてはしっかりとすじを通すために、局長と副市長に認識を伺います。
9月25日の常任委員会の中で、局長は、「アルコール検知器を各消防署に配置し、緊急車等消防車両の安全確実な運行確保の一助として活用しております」と説明されております。しかし、その後の聞き取りによれば、実態は違っています。全署所に配備されている102台のアルコール検知器のうち、動作確認をしても動かない機械が10台以上あり、さらに残りの検知器も10年以上経っているにもかかわらず1回も機器の補正の検査が行われていないという事実です。また、わが党の北谷議員も、先日保土ケ谷署で確認をしたところ、そこに配備されていた検知器はほぼ使われていなかったということです。
これでは、一般的に言えば、まともに動く機械は1台もなかったといっても過言ではありません。その状況を常任委員会審議の前に局長は確認していたにもかかわらず、アルコール検知器を「活用しています」と説明されています。これは明らかに不正確な説明で、とてもまともに活用ができる状況にあったとは言えません。
私は、当局の説明は足りていなかったと今でも思っていますが、局長はこのアルコール検知器の活用について、今の認識、伺います。

久保田消防局長:
常任委員会において、その時点で把握しておりました範囲内でご説明申し上げたところですが、各消防署における運用の方法が異なっておりまして、その詳細まで説明できなかったことにより、誤解を与えてしまった面もあり、その点については、申し訳ないと感じております。

古谷議員:
副市長、私たちは、限られた時間の中で、議案やまた請願を審査する際に、当局のみなさんの説明っていうのが信じられなくなったり、あるいは不正確なものであるということであれば、本当に議会での審議が成り立ちません。ましてや、局長が常任委員会の場で正式にご説明されたものが正確でなかったということであったら、その事実と違っている情報を信じて請願の採決を決めたとしたら、議会は何のためにあるのかというふうにもなります。林市長は日頃から二元代表の大切さをおっしゃっていますが、それにもそむくことにもなろうかと思います。副市長、これでいいんでしょうか。
柏崎副市長:
議会および市民のみなさまに丁寧にご説明するということは、常に重要なことだというふうに認識をしております。ただいま局長からも答弁がありましたように、各消防署における運用の詳細についてまでご説明できなかったことが十分でないとのご指摘につながっているものというふうに考えております。今回の件は、その時点で消防局が把握している範囲内でご説明したものですが、今後もみなさまにご理解いただけるよう、丁寧な説明が必要であると考えており、そのように努めてまいります。

古谷議員:
二度とこのようなことがないように、再度申し上げたいですし、私たち議会の側もしっかりと襟を正すべきところがあるというふうに思います。
市議団視察報告「韓国・カジノの実情」~よこはま健康友の会「暮らしとからだ」2015年10月1日号
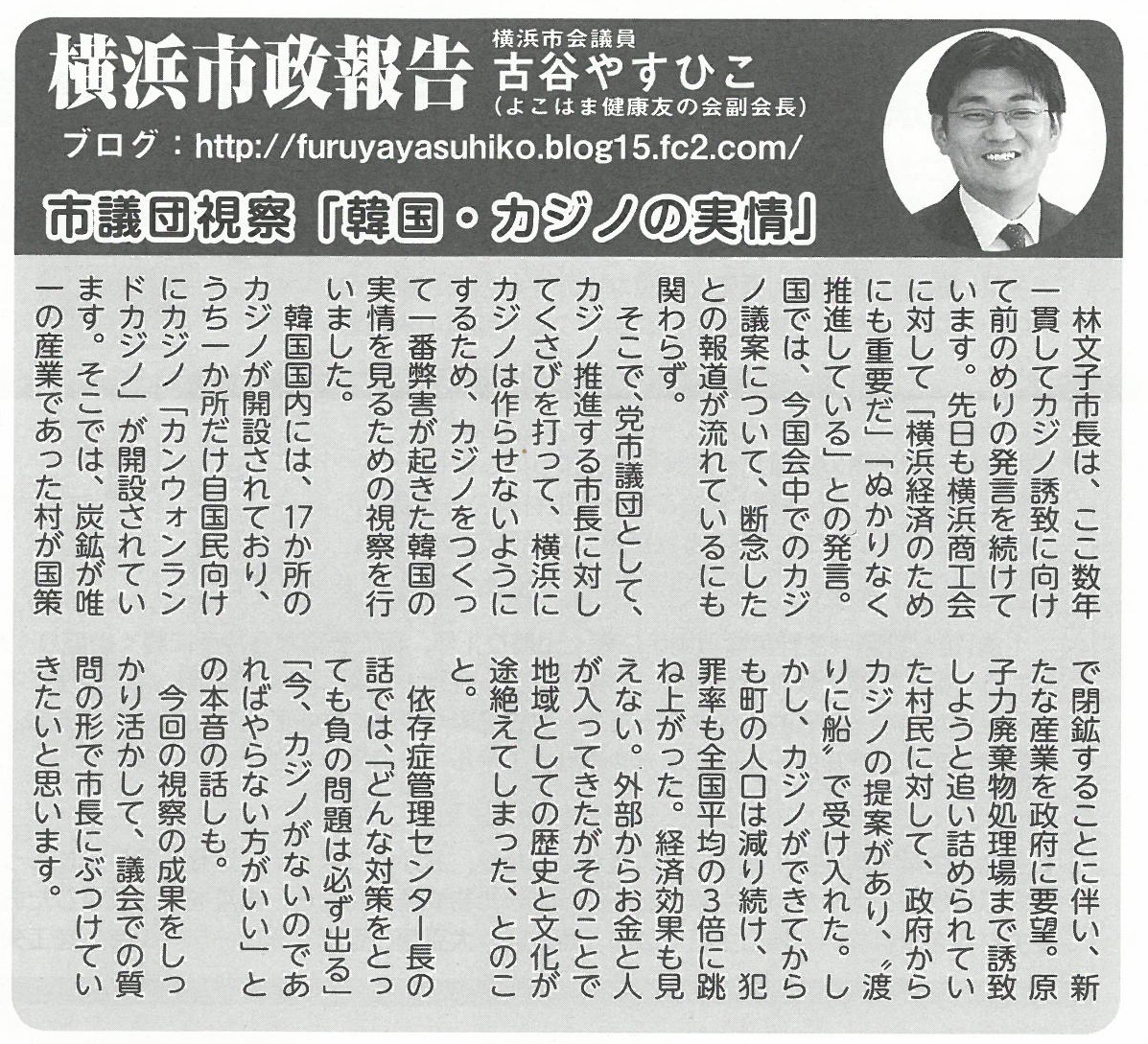
子宮頸がん予防ワクチンを接種しての副反応とみられる被害者にさらに積極的な支援を!!~10月1日 横浜市会決算総合審査での一問一答 (その五)
子宮頸がん予防ワクチン接種の副作用患者にさらに積極的支援を
古谷議員:
最後に、子宮頸がんワクチンの副反応の問題について。
子宮頸がんワクチンの予防接種が事実上ストップしてから2年以上経っています。本市は、他都市に先駆けて、因果関係は明確でない中、医療費援助などに取り組まれたことは、本当に評価したいというふうに思っています。その一方で、苦しまれている患者さんやそのご家族の方が、認定もされずに、またあちこちの医療機関を放浪しているということもよく伺います。今回、県で医療支援を行うことになったわけですから、本市では窓口機能は引き続き持つというだけではなく、さらに積極的に支援策を打ち出せば、さらに今もなお苦しんでいる患者さんやそのご家族の方の願いに寄り添うことになるというふうに思いますが、市長の見解、伺います。

林市長:
子宮頸がん予防ワクチン接種後に症状を訴える方への救済につきましては、お話の通り、先日国の審議会が開催されて健康被害救済のための速やかな審査の再開、学校生活を含めた生活面での支援の強化、原因究明に向けた調査・研究の推進など、今後の方針として示されたわけです。
横浜市といたしましては、これまで築いてきた患者やご家族の方との信頼に基づいて、引き続き相談を通じて、健康状態の把握に努め、医療面のみならず生活面の支援についても検討してまいります。

古谷議員:
名古屋市では、市内に住む7万人を対象にして、副反応の影響調査を実施すると発表して、これ全国でも最大規模の調査です。脱力感や歩行困難などの代表的な症例の有無や、接種していない人との差を調べるということです。名古屋市長は、「名古屋だけではなく、日本全体のワクチン行政にとってプラスになる」と話しています。調査対象を大規模にすればするほど、疫学的にも有効な調査になります。本当に、患者さんを励ますことなる上に、有効な啓発にもつながります。日本一の人口をかかえる政令都市の横浜が実施に踏み切る意味は大きいと思いますが、市長の見解、伺います。
林市長:
国は専門家を中心とした研究班を設置して、ワクチンと接種後に生じた症状との因果関係を研究するため、全国規模で調査を行う方針を示しております。国が調査を行うにあたっては疫学的にも有効な調査となり、接種後の症状で苦しむ市民のみなさまの救済につながるよう、横浜市も全面的に協力してまいります。横浜市は基礎自治体として引き続き患者や保護者からの多様な相談を通じて、接種後の症状やその後の体調の変化、通学状況等の経過を確認し、きめ細かく健康状態の把握に努めてまいります。
古谷議員:
今もなお、子宮頸がんワクチンの副反応で苦しんでいられる患者さんというのにぜひ思いを馳せて、対策をぜひリーディング都市として進めるように要望して、質問を終了します。
横浜のカジノ誘致問題について、マイナス面の数値的言及がないIR報告書は政策判断を誤らせる!! ~10月1日 横浜市会決算総合審査での一問一答 (その四)
マイナス面の数値的言及がないIR報告書は政策判断を誤らせる
古谷議員:
次に、本市のIRという名のカジノの誘致の問題について、伺います。
史上最長に延長された先の国会でも、カジノ議案は1回も議論されることなく終わりました。そんな中で、本市は昨年も1,000万円、今年も1,000万円の予算を計上して、カジノ誘致に向けての調査を行っています。そこで、昨年本市が依頼して「IR等新たな戦略都市づくり・検討調査報告書」について、順次伺っていきます。
私たちは、この報告書を専門家に依頼して分析をしてまいりましたが、一言で言って、結論の出し方が恣意的で、数字の当てはめ方も非常に乱暴だと感じています。
まず、カジノ導入についての影響評価ですが、プラスの影響だけではなく、マイナスの影響も含めて論じなければ、正確な影響評価はできないと思います。たとえば、アメリカのニューハンプシャー州のカジノ導入の際の報告書では、ギャンブル依存症対策の公的負担やギャンブル依存症者の増大による社会的コストの推計を行った上で、自治体にとって財政的にプラスなのかマイナスなのか、総合的な評価をしています。今回の報告書には一切そういったマイナス効果についての数字的言及がありません。
市長、これはカジノ誘致による経済効果を願う立場の方から見ても、政策判断を誤るような内容的に非常に不十分な報告書だと思いますが、見解、伺います。

林市長:
昨年度実施した委託検討調査でございますが、IRの基礎的な内容を把握するために実施いたしました。具体的には、IRの概要や諸外国における導入の効果のほか、カジノにより懸念される事柄とその対策などを整理したほか、産業連関分析により一般的な経済効果の算出などを取りまとめたということでございます。

古谷議員:
プラスの効果は無理やり数字を出しているんです。マイナス効果は、述べただけで、数字的には言及していません。これは間違いありません。
たとえば、横浜のIRカジノへの訪問客数567万人来ると推定されています。前提となっている博報堂の調査、これは「全国20の都市にカジノができるという前提で、あなたはカジノに行きたいと思いますか」という質問です。これを、横浜の報告書では、東日本でIRに行きたい人ということは、全て横浜に行きたい人というふうに読み替えさせています。こんな、あまりにもひどい推計だというふうに思っています。
市長は、このIR誘致に向けてこの間積極的な発言をされています。9月5日付けの神奈川新聞では、「すごく有力な手段で、これからの横浜の経済成長には非常に重要なこと」だと、横浜の商工会議所の佐々木会頭との懇談でお話ししていると出ています。なぜそこまで前のめりで、市長はIRを導入すれば経済効果があがると信じておられるのか、その根拠は何か、伺います。
林市長:
IRは、今年6月国が成長戦略として閣議決定した日本再興戦略においても、観光振興、地域振興、産業振興等に資することが期待されるとして位置づけられております。
私が前のめりっていう言い方、今、先生おっしゃったんですが、別の機会にも話をしておりますが、東京都の隣におりまして、法人税が1兆3,000億でしたか、それ近く入る東京都と、372万人もいながら法人税が640億程度というこの横浜市。なんとあっても、私も先生と同じで、福祉とか医療とか子育て支援、そういうことが本当に大事だと思いますが、いかんせん税収がなければやりきれないところでございます。ですから、そういう意味で、これだけの上場企業の格差がある950に対して53しか上場企業がないっていうことで、税収で非常に苦しんでおりますから、そういう意味で有力な手段のひとつだというふうに考えております。
ただ、懸念される事柄というのは、すごっくあるわけですよね。そういうことについても、国もすごく検討しておりますし、調査していくことは大事なことでございますので、引き続きマイナスの影響も含めて、検討してまいります。
古谷議員:
今回の本市の報告書の中で、犯罪の増大なんかについても触れてあります。しかし、これについては、カジノが犯罪を増加させるための十分なデータはないというような記述になっています。しかし、私たちは、報告書の検討を依頼した静岡大学の鳥畑教授によれば、これは意図的な歪曲であるというふうに指摘をしています。米国の報告書の原文のその部分を読めば、カジノがギャンブル依存症を増大させること、ギャンブル依存症の犯罪発生率が高いことを示しながら、しかしながらカジノと犯罪率の増大を定量的に結論付けるだけのデータが不足しているということで、今後の研究が必要であると結論を留保したにすぎません。カジノが犯罪を増大させないと結論づけたものではありません。さらに、その後に報告されているニューハンプシャー州報告書では、その後の研究成果を踏まえてカジノが犯罪を増大させることについては研究者の見解が一致していると、逆にこちらでは結論付けています。そして、議論はなぜカジノが犯罪を増大させるのかに移っています。
横浜市ならびに首都圏という人口密集地でカジノをつくることの弊害がこれから顕在化するのであり、大量のギャンブル依存症者やギャンブル被害者が生まれることになります。それに伴う自治体の費用増大や社会的コストの増大が、報告書に示されている60億円という税収増に見合うものになるのか疑問ですが、見解を伺います。
林市長:
カジノに対してはさまざまなご意見があると思います。そして、先ほども申し上げました最初の委託の検討調査というのはIRの基礎的な内容を把握するために実施したものでございますから,これが全部ベースになって、私どもが絶対IRへの導入の中のカジノがいいというふうに申し上げるものではございませんので、これから十分に調査検討を進めていかなくてはなりませんし、また国の方も法案が通っておりませんので、これも国の動向を見ていかなくてはならないというふうに私は思います。
もちろん先生ご懸念の犯罪の問題とか、いろいろな各国に事例もあるでしょうし、また逆にいい例もあると。先ほども何度も申し上げておりますけど、税収が厳しい、なかなか都市に一極集中していく隣で厳しい思いをしている中での有力なひとつの手段ではないかと、私、今現在考えているところでございますので、市民のみなさまにも先生のご懸念にもきちっとご説明ができるようにしてまいりたいと思います。まだ、そこまで行っている段階ではございませんけれども、そういうのを覚悟して、今厳重に調査もし、ご理解、納得していただいて、たとえばやるとすればできることであるかというふうに考えております。
古谷議員:
団として、この8月に韓国を訪れて、カジノとギャンブル依存症の関係について調査を行ってまいりました。韓国では、韓国人が入れるカンウォンランドを訪れる方は年間約300万人。その0.3%が依存症のリスクが高いといわれています。そのため、カンウォンランドカジノの真向かいには依存症対策センターが設置されており、入場制限を行うとともに、一定日数以上の入場者にはカウンセリングが義務付けられています。さらに、首都ソウルには、ギャンブル問題管理センターがあり、カジノだけではなく、公営ギャンブルである競輪・競馬を始め、違法のインターネットギャンブルなどの依存症などについて、予防、治療などを、今も行っています。
ひるがえって見れば、今の現状の横浜市でも、さまざまな公営ギャンブルの場外売り場があり、諸外国では完全にギャンブルであるパチンコ・パチスロはあちこちにある状況。昨年度で言えば、パチンコ屋内などでの刑法犯罪は警察庁の報告では2万人を超えています。そんな状況ですから、今でも依存症の対策、この横浜でも必要だと思いますが、市長の見解、伺います。
林市長:
現状では各区役所では心の健康相談センターにおいて、アルコールなどの依存症全般に係る相談の中で、いろいろそういうギャンブル依存症対策等々やっているわけでございます。具体的には相談の内容に応じて、専門の医療機関の受診や回復に向けた施設利用を促すなどの取り組みを行っております。ギャンブル依存症を含めた依存症への対策は、市民のみなさまの心の健康の保持・増進の観点から必要だと考えておりまして、今後とも専門の医療機関などの関係機関と連携をしながら、本人や家族への支援や職員の人材育成について引き続き取り組んでまいります。
古谷議員:
いろいろ言われたんですが、実際はほとんどやられてません。
あらためて、あらゆる点から見て、IR誘致はぜひやめるべきであるというふうに思いますし、いますぐにもギャンブル依存症の対策、これ横浜にも必要だというふうに主張しておきます。
