日本共産党横浜市会議員
古谷やすひこブログ
横浜市の教員で少なくとも459人が過労死ラインを超えていることが判明!! ~2017年12月19日付けのしんぶん赤旗・首都圏版に掲載されました
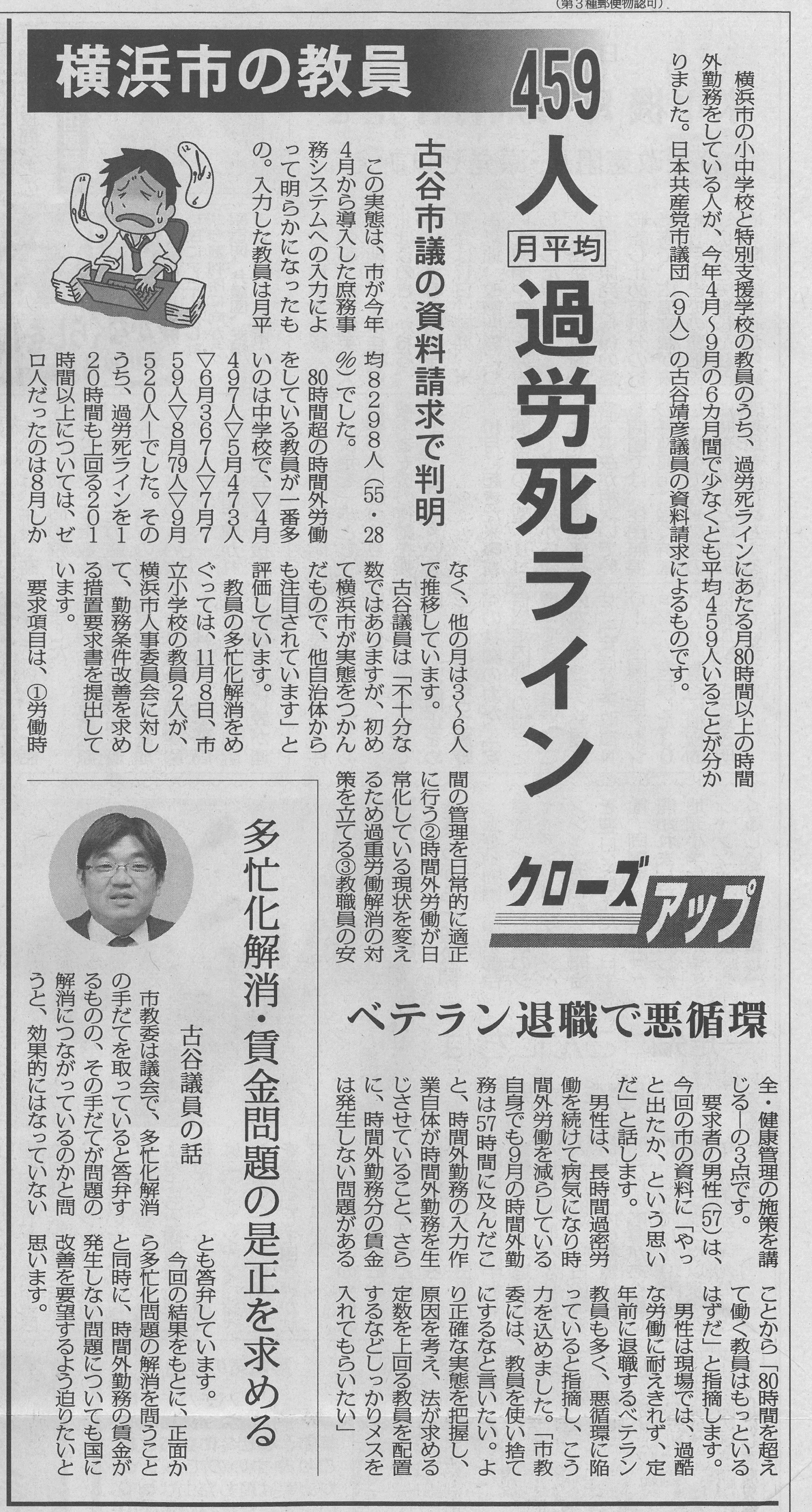
「黙ってこの事態をやり過ごしてしまうことは、議会としての自殺行為です!」 不倫疑惑のスキャンダル報道をめぐる請願審査で採択少数で否決されました! ~12月12日の横浜市会運営委員会での議事録【速報】
本日の横浜市会運営委員会で、11月半ばに週刊誌やテレビなどで報道された横浜市会議員の「不倫スキャンダル」疑惑についての二つの請願が出されて、それについて審議が行われました。 それに先立ち、委員会室での直接傍聴願いが二人の方から出され、審議がされましたが「委員会室が手狭なのでモニター室での傍聴をお願いしたい」との意見が自民党・民進党・公明党から出され、私たちは「傍聴願いを出している方はお二人だけなので十分にスペースはあるので許可するべき」と主張しましたが、「市会運営委員会の直接傍聴許可に賛成」は少数で、許可されませんでした。 続いて、出された二つの請願について各会派からの態度表明。(以下、事務局でおこしたものです。) 清水 富雄議員 自由民主党 議会外における、議員個人の行動については、議員自らが責任を持つものであり、議会が議員個人の行動に関与すべきではないと思いますし、一連の経緯の中で、一定の責任をとっていると思われますので、議員辞職を求める必要もないことから、請願二件について不採択でお願いしたいと思います。 麓 理恵議員 民進党 今回、出されていることは、議会運営に影響を与えるものではありませんし、先ほど○○だったように、大変個人的なことだと考えていますので、調査特別委員会を設置するようなことは必要ないと思います。また、この議員の出処進退は、自身で決めるとというふうに考えていますので、この二つの請願については不採択でお願いします。 尾崎 太議員 公明党 私どもの会派も、私的事項ということですので、議会で対応するものではないと思います。 最後に、日本共産党議員団として、私が以下の通り発言しました。
請願第12号 市会議員の疑惑解明のための調査特別委員会の設置について 請願第13号 市会議員の疑惑解明等について 【日本共産党横浜市会議員団としての見解】 日本共産党横浜市会議員 古谷やすひこ 日本共産党議員団として本請願について「採択すべき」として意見表明して以下の通り理由を述べます。 本件は、11月半ばに週刊誌やテレビなどで報道された横浜市会議員の「不倫スキャンダル」疑惑について、その疑惑の解明などを求めるものです。それぞれの請願について、請願趣旨をそのまま読めば一般市民から本請願が提出されることもよく理解できます。 請願第12号に述べられている通り、市会議員の政治倫理について横浜市議会基本条例で明確に定められています。第4条には「市会議員は次に掲げる原則に基づき活動するものとする」として、その2項の3には「 自らの資質の向上に不断に努めるとともに、高い倫理性を常に確立し、誠実かつ公正に職務を遂行し、議会及び自らの活動を市民に分かりやすく説明すること。」と明確に記されています。また第28条にはそのものずばり「政治倫理」の規定が定められており、「議員は、市民の負託に応えるため、政治倫理の向上に努め、公正かつ誠実に職責を全うするとともに、市民の代表として良心及び責任感を持って、品位を保持し、識見を養うよう努めるものとする。」とされています。請願第12号ではこれらの規定が定められた議会基本条例に違反しているのではないかと指摘しています。現在のところ、報道が出されて以来、当事者からの表明は一切ありません。その一方で自民党市会議員団を離団したり、国際港湾経済委員会の副委員長を辞任したりしていますが、その理由についても何も述べられていません。このまま横浜市会議員として公職の立場に就き続けるのであれば、市民に対して何らかの表明をするのは市会議員として当然です。議会側もそのことを求めるべきです。そのことも求めないというのでは、市民から見れば議会側も何も発信しない、議論もしない、と受け止められます。本当にそれでいいんでしょうか。異様な状態だと思います。今回のことでは横浜市会としても傷つけられている状況です。 今回の件がもしその指摘に当たらないとして請願を否決するのであれば、少なくとも今回の「不倫スキャンダル報道」について、横浜市の議会基本条例には違反していないことを論証すべきです。公務外であるから条例違反に当たらないと言われるかもしれませんが、それでは市民理解は得られるはずがありませんし、横浜市会議員の身分でなければ報道もされることはありませんでした。また何よりも私たち自らが議論をして定めた議会基本条例をないがしろにして、黙ってこの事態をやり過ごしてしまうことは、議会としての自殺行為です。 私たち議員は、日本国憲法や地方自治法など様々な法律や条令のルールのもとで働いている特別公務員です。たとえその中に、理念的な性格を持つものであったり罰則規定がないものだとしても、率先して国民市民の規範となって働くのが議員の役割だと思います。 よって本請願について採択することを重ねて呼びかけます。 以上  残念ながら、両請願とも「採択すべき」に挙手したのは、日本共産党だけで、委員会としては否決されてしまいました。
残念ながら、両請願とも「採択すべき」に挙手したのは、日本共産党だけで、委員会としては否決されてしまいました。
「ようこそ滞納いただきました!? 滞納者の『生活再建』に向き合う野洲市(滋賀県)を視察」 ~週刊市政ニュース「こんにちは 古谷やすひこ です」の最新号(2017年12月6日)
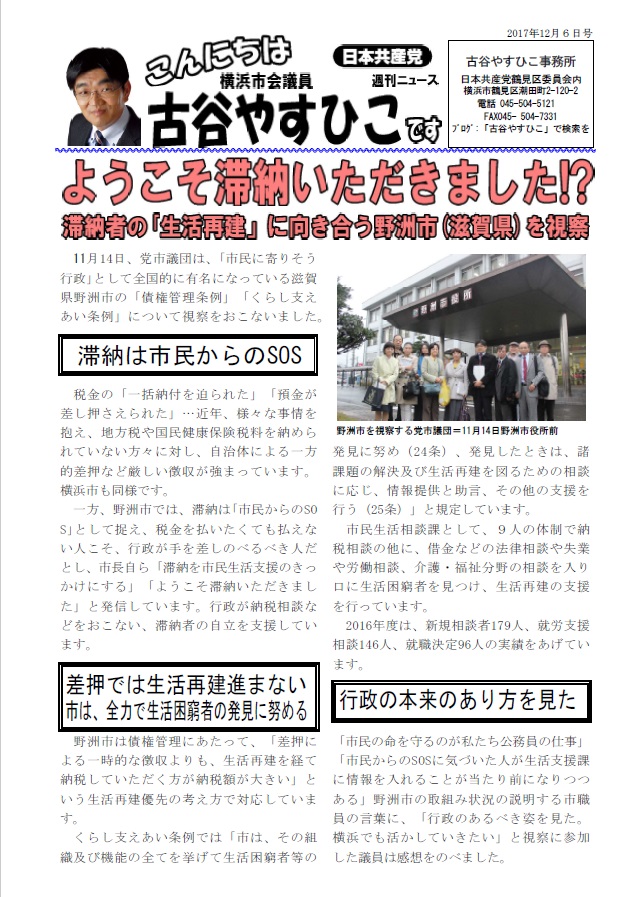
高速道路建設で地盤沈下!? ~「暮らしとからだ」2017年12月1日号
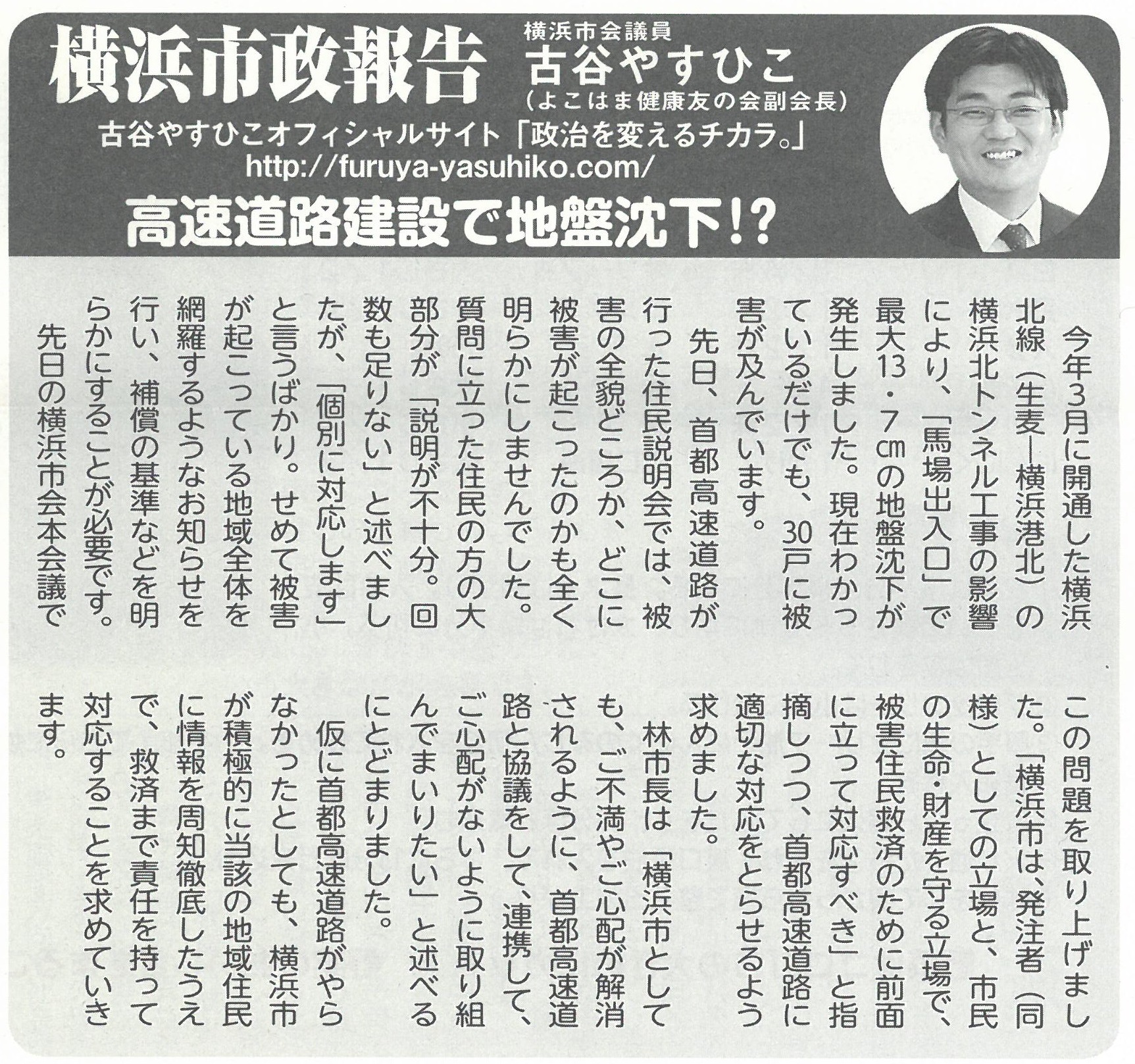
鶴見駅周辺に公衆トイレの設置を! ~タウンニュース鶴見区版(2017年11月30日)に私の記事が掲載されました

