日本共産党横浜市会議員
古谷やすひこブログ
成績表が平均4以上のできる子優遇の奨学金制度は改めよ ~横浜市会予算特別委員会の教育委員会審査での一問一答の様子 その②
できる子優遇の奨学金制度は改めよ
古谷議員:
続けて、高校奨学金の問題について伺います。本市の高校生向けの奨学金制度について、成績要件を課している意味について、伺います。
小口国際教育等担当部長:
本市の高等学校奨学金は、条例の趣旨に基づき、学業成績が優秀であるにもかかわらず、経済的な理由により就学が困難な者に対して給付しているものです。そのため、給付にあたっては成績要件を設けております。
古谷議員:
本市の子どもの貧困対策の計画の中に、「世帯の所得が高い方は学力は高い傾向にある」また「貧困状態にある子どもは学力や進学の機会において格差が生じている現状があります」と述べられ、高校進学後の支援の必要についても言及されています。人材を育成するんだというのであれば、できる子だけが道が開けているという今の施策だけでは非常に不十分だというふうに思います。もう一方で、できる子だけの枠ではなくて、「貧困の連鎖を断つ」というため、学ぶことを応援するような性格の奨学金のあり方、ぜひ検討が必要だというふうに思いますが、教育長いかがでしょうか。
岡田教育長:
経済的に就学が困難な世帯へは、26年度から就学支援金制度や、生活保護世帯および市民税所得割非課税世帯を対象とする高校生奨学給付金制度によって、支援が行われています。そして、本市の高等学校修学金は、これらの制度と重複して支給が可能であり、経済的に困難な状況がありながらも、学業に熱心に取り組む生徒にとっては、進学準備などにかかる経費の一部となっております。引き続き、現状を注視してまいります。
古谷議員:
ですから、上乗せされているとわけですから、そういうところにも、できる子だけの枠をつくるというのではなくて、ぜひ検討していただきたいというふうに思います。
業者弁当「ハマ弁」ではなく就学援助の対象となる中学校給食を ~横浜市会予算特別委員会の教育委員会審査での一問一答の様子 その①
業者弁当「ハマ弁」ではなく就学援助の対象となる中学校給食を

古谷議員:
まず、ハマ弁について伺います。
昨年の第3回定例議会の総合審査の中で、昼食が食べられないでがまんする生徒について、「なくなるようにちゃんと対応をしていきます」と教育長はその時、回答ただきました。その認識について変わりないかどうか、伺います。

岡田教育長:
認識に変わりはございません。
古谷議員:
ありがとうございます。教育長は、昼食の用意が困難な生徒、これは何人位だというふうに検討されていますか。
岡田教育長:
市立中学校の生徒約8万人の1%800人程度を想定しています。今まで、ヒアリングの中では、昼食の用意が困難な生徒はいないという学校が多く、またはいても非常にわずかだというふうに聞いております。一方で、学校現場からは支援の制度が整備されるのであれば利用したいという意見もいただいており、それらをふまえて1%と想定いたしました。
古谷議員:
まだ根拠まで聞いてなかったんですけど、1%という、その800人というのが、非常に曖昧だというふうに思うんですけど。その点いかがでしょうか。
岡田教育長:
今いろいろ現場の調査をしておりますけれども、これ以上の数字は今出ていないというのが現状です。
古谷議員:
今現在、市内の中学生で1万3,003人の就学援助を受けている中学生が今います。その中で、今おっしゃるとおりだと、800人しか想定してないということになるんですが、その800人も根拠がないというふうにもしなるとすると、あまりにも計画自体がちょっとずさんじゃないかというふうに思うんですけど、いかがでしょうか。
岡田教育長:
学校現場を熟知している教員へのヒアリングに基づくものです。
古谷議員:
教育長、ぜひ、もし800人、これ想定されているんですけど、想定を超えた場合、どう対応されるのか、伺います。
岡田教育長:
きちんと調べて、必要性があれば対応してまいります。
古谷議員:
ぜひ、現場からの申請については100%対応していただきたいというふうに思います。
そもそも、就学援助について伺いますが、就学援助は学校教育法の第19条で「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」と規定されています。その法が定めている「必要な援助」の内容についてですが、小学生と中学生では変わってはいけないというふうに思いますが、どうか伺います。
岡田教育長:
変わってはいけないという意味がちょっと理解できないんですけれども、たとえば、中学生になると部活があります。そういう意味で、就学援助の支給品目は国の基準に基づいて定めておりますので、そこは違っています。
古谷議員:
違っている中味は何でしょうか。
岡田教育長:
一番大きいのは、修学旅行費も大きいですし、体育の実技用具なども大きいと思います。それから、部活の活動費なども、生徒会費、そういうものも大きいと思います。
古谷議員:
現在、本市が経済的理由で就学援助が本市が必要であるというふうに認定されている中学生が1万3,003人いらっしゃるわけですが、もちろんハマ弁は、給食ではありませんから就学援助の対象にはなりません。ですから、新たな基準をつくらなくてはいけなくなったわけですが、根拠も定かではありませんし、合理的では私はないというふうに思います。しかも、想定人数が少なすぎます。教育長は、本市で1回認定した1万3,003人の就学援助認定者を、また別の物差しを使って、さらに絞り込むような審査をするのはあまりにも酷だというふうに思いますが、いかがでしょうか。
岡田教育長:
就学援助の受給世帯の生徒もきちんと昼食は持ってきていると、学校現場からは聞いております。このため、生徒や保護者ががんばって昼食を用意していることも大切に考えたいと思っています。その上で、どのような生徒に支援するか、学校現場からの意見を聞きながら、ガイドラインの作成に向け、検討を進めているところです。
古谷議員:
教育長、学校現場から聞いているとおっしゃるんですけど、詳細なアンケート、取ってないはずなんです。しかも、今、昨年、横須賀の教育委員会が非常に詳細なアンケートを取りました、現場から。それによっていろいろ対応を変えているわけですが、横浜市もこれ、ぜひやるべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。
岡田教育長:
ガイドラインの作成の方法につきましては、いろいろ検討しているところですけれども、生徒のプライバシーに関わる問題でもありますので、実態調査の仕方というのは非常に慎重にやるべきだというふうに考えております。その上、きちんと機会をとらえて調査は実施していきたいと考えています。
古谷議員:
ぜひ、実施するのであれば、PDCAサイクル回すためにも、実態のアンケートをきちっとやらないといけないというふうに思いますよ。その点、いかがでしょうか。
岡田教育長:
繰り返して申し訳ありませんけれども、きちんと学校の現場の状況は把握したいと考えておりますので、先生方のご意見はきちんと聞き、また生徒のプライバシーも大事にしながら、学校毎の個別のヒアリングを実施したいと考えております。
古谷議員:
ぜひ、実態調査っていうのはきちっとやっていただきたいというふうに思います。
本来、横浜市が中学校給食を実施していれば、1万3,003人の就学援助認定者の方は、年額で6万円の補助があるわけです。それが、本市は給食を実施しないわけですから、せめて就学援助を受けている人には、本市事業のハマ弁の購入費、支給するのは妥当性があるというふうに思いますので、強く要望しておきます。
大阪市では現在注文式のデリバリー給食で、ハマ弁との違いは、それは給食と位置付けるのか位置付けないか、それだけの違いだというふうに思います。その大阪市では、温かい汁物が付くものの冷たいおかずのために食べ残しが異常に多くて、改善を図ったものの効果が上がないということで、デリバリーから学校調理方式へ転換が図られています。
また、横須賀市では、業者にパンや弁当を注文するスクールランチを実施していましたが、注文率が低調で、アンケートで小中学生の保護者の多くが小学生と同じ完全給食を支持しているということから、スクールランチ拡充を断念して中学校給食の実施の検討を始めています。
これら大阪や横須賀での先行事例をみても、横浜も同じ轍を踏んでしまうのではないかというふうな危惧がぬぐえませんが、ハマ弁が失敗しないという根拠は何か、教育長の見解、伺います。
岡田教育長:
同じような轍を踏まないようにしっかりやりたいと思いますけれども、ハマ弁には注文、支払い手続きが簡便で、おかずが選択でき、汁物、牛乳も単品で注文できるといった他の都市にはない特徴がありますので、多くの方に利用していただきたいと考えています。
古谷議員:
そうすると、横須賀や大阪が撤退したのは、汁物の問題と注文方法だけの問題だというふうにお考えですか。
岡田教育長:
一番大きいのは注文の仕方ではないかなと思っておりますけれども、大阪の場合はまた全然違いますので、ちょっと参考ではないというふうに考えています。
古谷議員:
ぜひ、喫食数が少なくなりすぎて、事業者が撤退してしまうというようなことはないかどうか、確認で、伺います。
岡田教育長:
事業者には食数の保障はしない条件で公募に応じていただいておりますし、食数が少ないことによる事業者撤退はないと考えています。
古谷議員:
神戸市では、デリバリー方式の給食が行われていましたが、86件の異物混入が明らかとなって、社会問題になりました。その際、業者の基準違反に対して行政の指導監督確認が果たせないという状況になってしまいました。本市でも、そうならないように、異物混入対策、事故の対応について、当然、横浜市が学校現場で提供されたハマ弁で問題が起こった場合、教育委員会が全面に立って解決に向けてその役割を果たすべきだと思いますが、どうか伺います。
岡田教育長:
お弁当の製造過程や配達時に起因する問題の場合は、事業者が全面的に責任を負うことになりますけれども、再発防止に向け、本市としても、事業者と一緒に、もしそういうことが起きた場合には、しっかり取り組んでいきます。
古谷議員:
もし、こういった場合起きた場合に、そういった言い訳は、ぜひ生徒やあるいは保護者に向けてはしていただきたくないというふうに思います。
私はやはり、この件、いろいろ指摘させていただいた中味考えても、中途半端な注文式の今回のような注文式の業者弁当でなくて、改めて学校給食法に基づいた中学校給食の実施を求めます。
カジノ建設の見直しを ~2月23日付のしんぶん赤旗・首都圏版に掲載されました
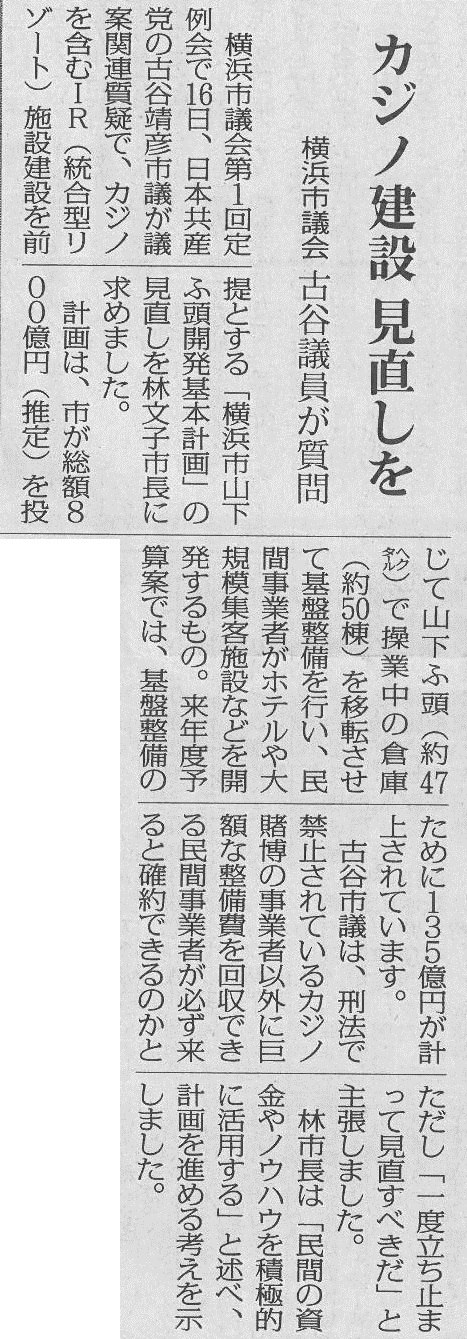
[本会議質問の一問一答] 二つの大きな巨大インフラ整備問題「山下ふ頭再開発に巨額を投じる大博打はやめよ」「新市庁舎移転新築計画は立ち止まって再検討を」 ~2月16日 横浜市会議案関連質問での質疑のその様子 ⑤
山下ふ頭再開発に巨額を投じる大博打はやめよ
古谷議員:
次に、市第207号議案「横浜市山下ふ頭開発基本計画検討委員会条例の廃止」についてであります。
わが党は、一貫して山下ふ頭開発が多くの反対の声が出ているカジノ含むIRの誘致が前提となっていると指摘してきました。実際、検討委員会議事録をみても、すでにIRが前提となった議論が行われていることがよく分かります。多くの市民がその導入を反対しているIRが念頭に置かれた基本計画を市長に答申したまま、委員会を廃止することは許されません。
そもそも、47ヘクタールという広大な土地に建つ49棟もの操業している倉庫を立ち退き移転をさせて基盤整備を行い、それを民間事業者の開発に委ねるというもの。来年度予算案でも134億の市債を発行して、すべての完成までにはその5倍から6倍もの巨費を投じるものと予想されます。さらに、2025年までに全体を共用する予定という計画で、いわゆる「2025年問題」で扶助費が急増すると言われていて、現在それに向けて様々な準備が行われている横で、こんな巨額な事業費を投入することに市民理解が得られると思うでしょうか。市長の見解を伺います。
また、市長は、カジノ事業者以外にこの巨額な整備費を回収できるような民間事業者が必ず来ると確約できるのでしょうか。それこそ、この大博打に横浜市民を巻き込むようなやり方はやめていただきたいと思います。一度立ち止まって見直すべきと思いますが、市長の見解、伺います。

林市長:
市第207号議案について、ご質問いただきました。
多額な事業費を投入することに対する市民理解についてですが、横浜港における物流の主力が沖合展開する状況の中で、今後の横浜の成長エンジンとなる都心臨海部の新たなにぎわい拠点の形成をめざすため、山下ふ頭を再開発することについては、横浜市中期4か年計画において位置付けております。これを踏まえ、26年9月から4回にわたって横浜市山下ふ頭開発基本計画検討委員会で議論を重ね、節目ごとに市会への報告や市民意見をお聞きした上で、27年9月に横浜市山下ふ頭開発基本計画を策定しておりまして、これに基づき事業を進めてまいります。
民間事業者の見通しが立たない基本計画は見直すべきとのご意見についてですが、山下ふ頭は周囲の静音な水域や横浜の観光スポットに隣接した広大な空間などの開発ボテンシャルを有しております。このため、民間の資金やノウハウを積極的に活用して、都心臨海部における新たな魅力を作り出していくことができると、私は考えております。計画通りに進めてまいります。

新市庁舎移転新築計画は立ち止まって再検討を
古谷議員:
最後に、市第213号議案「横浜市市庁舎移転新築工事請負契約の締結」についてであります。
私たち日本共産党横浜市会議員団は、この新市庁舎建設問題について一貫して問題提起をしてきました。私たちは、市庁舎そのものの建て替えは否定していません。それは、時期と金額が問題であります。時期については、耐震補強をした現庁舎がまだ使える状況であることや、市庁舎の建て替えが必要な場合は将来世代に過度な負担にならないような費用に抑えるべきことが肝要です。市長も就任当初は、市庁舎の建て替えには慎重な態度をとらえていましたが、一転、現計画の推進にアクセルを踏んでしまいました。誠に残念です。
予算が厳しいといわれている中に、異常な高額な事業費の支出、考えられません。また、いまだ新市庁舎建て替えに市民オンブズマンからは提訴がされていることや、横浜市公共事業評価制度に基づく市民意見募集で今計画に対して出された多くの反対の声に、市長はいまだ答えていません。これから大都市制度の中で、都市内分権を進め、区役所機能を拡充しようとしている時に、一つの市役所を大きな庁舎にするという方向は政策矛盾です。危機管理上の問題もあります。また、現計画が粛々と進められると、移転後の関内駅前は空洞化することも懸念されます。
やはりこの際、このまま契約に進むべきではなく、立ち止まって検討するという英断をして、市民の皆さんの願いに応えるべきと思いますが、市長の見解を伺って、一旦質問を終えます。
林市長:
市第213号議案について、ご質問いただきました。
新市庁舎計画に関する裁判や反対意見についてですが、27年11月の横浜地方裁判所一審判決では、新市庁舎整備に関する本市の手続きを違法・不当とする原告側の主張は退けられ、これまでの本市の取り組みは適切であったと認められたものと受け止めております。新市庁舎の整備については、さまざまなご意見があるだけに、これまで議会においても出来る限り丁寧に説明しながら進めてまいりました。今後とも、関内関外地区の活性化と、現市庁舎が抱える喫緊の課題の早期解決に向けて、しっかりと取り組んでまいります。
[本会議質問の一問一答] 公立で受験難関校で開設することについての見解、教育長の全く回答をしていない答弁を見てください ~2月16日 横浜市会議案関連質問での質疑のその様子 ④
義務教育学校の導入を学校統廃合の手段にするな
古谷議員:
次に、市第205号議案「横浜市立学校条例の一部改正」です。この議案には3つの改正内容があり、そのうち昨年改正された学校教育法での9年間の「義務教育学校」という新たな校種が創設され、小中一貫校の霧が丘小中学校を義務教育学校に移行するというものについて、伺います。
小中一貫の義務教育学校の導入の目的の一つにいわれているのが「中一ギャップ」の解消と、こういったものも言われていますが、その根拠はありません。実際、文科省の国立教育政策研究所が発表した「不登校・長期欠席を減らそうとしている教育委員会に役立つ施策に関するQ&A」、この中に「『中一ギャップ』の正しい理解」とあり、その中のデータからは「さほど大きなギャップは感じられません」と、自らが結論付けています。
また、逆に審議会の答申などでは、小中一貫校の課題として「人間関係の固定化への対応」「転出入への対応」「小学校高学年におけるリーダー性の育成」「中学校の生徒指導上の小学生への影響」などが挙げられています。また、さらなる教員の多忙化も非常に心配です。
そこで、教育長に伺います。本市で小中一貫の義務教育学校の導入をするのであれば、挙げれている課題、どう解消するか提示されて当然だと思いますが、教育長にその対策、伺います。
法改正を通知した政令をみても、義務教育学校の導入目的が学校統廃合の手段としかみえないような書きぶりがあります。他の自治体では、小中一貫校の導入を学校統廃合とリンクさせていますが、本市はそういうことをするべきでないと思いますが、教育長の見解、伺います。
また、今回の条例の改正で横浜サイエンスフロンティア高等学校に併設型の中学校を新設するということについて、横浜サイエンスフロンティア高校が市内でも超難関のエリート校化していることも鑑みると、当然新設される中学校もそうなるであることは自明であります。2012年に開設された南高等学校附属中学の設置の際に、私たちは「受験競争の低年齢化に拍車をかけることになる」と懸念を表明しました。実際その通りになっており、市内の進学塾では南校附属中コースが設置され、今回の受験でも7.62倍の高い倍率となっています。さらに、今議案が通ることが折り込み済みのように、既にサイエンスフロンティア高附属中のコースが主要な塾には設置されています。こういう受験競争をあおるような超エリート校を整備するということをなぜ公立がやらなければならないのか。公立学校間での格差を持ち込むやり方は許されません。公教育の大きな使命とは、教育の機会均等と、等しく基礎学力の向上を身につけさせることであります。公の役割から逸脱したやり方で、しかも格差と貧困を結果的には広げるようなやり方だと思いますが、教育長の見解、伺います。

岡田教育長:
市第205号議案について、ご質問いただきました。
指摘される小中一貫教育の課題への対応についてですが、人間関係の固定化については、学校の規模が大きく影響します。9年間を通した多様な交流は、豊かな人間関係が構築できるものと考えております。転出入への対応につきましては、転入時に行う丁寧なガイダンスなどで引き続き対応していきます。小学校高学年におけるリーダー性育成について示されている工夫につきましては、これまでの小中一貫校の中でも実施しております。さらに、学年ごとに自らの成長を確認できる取り組みを考えています。生徒指導上の影響については、上級生下級生の関係が改善して、よい効果をあげていますので、本市の取り組みを積極的に発信していきます。
学校統廃合の手段として義務教育学校を導入すべきではないとのお考えについてですが、国の通知では、義務教育学校の制度化は小中一貫教育を円滑かつ効果的に導入できる環境整備するためのものであり、学校統廃合の促進を目的とするものではないとしています。本市においても、小中一貫教育をいっそう推進するために、義務教育学校を設置するものです。
横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校の開校は、公立学校間での格差を広げるのではないかとの考えについてですが、中高一貫教育校は、従来の中学校、高等学校の制度に加えて、生徒や保護者が6年間の一貫した教育過程や学習環境のもとで学ぶ機会を選択できるようにしたものです。本市におきましても、経済的な負担が少ない公立学校として、中高一貫教育校を設置することで、子どもの多様な学びの場を提供することができると考えています。
以上、ご答弁申し上げました。

横浜サイエンスフロンティア高附属中学選抜に低所得者優先枠を
(第2質問)
古谷議員:
質問は、教育長に伺います。附属中学について、低所得者世帯にも、いろんな多様なコースをもし用意するとおっしゃるのであれば、そういった低い所得の方でも優先的に入れるような枠をつくらないと、すべきじゃないでしょうか。それもしないで、多様なコースを開くんだというのは非常に欺瞞です。実際、塾に通わなければなかなか合格することはかないません。塾は月に数万円も塾代支払わなければなりませんから、現実的に道が開いていないというふうに思います。ぜひ、おっしゃるのであれば、低所得者向けの優先的に入れるようなすべを検討すべきと思います。質問です。
岡田教育長:
横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校の件で、ご質問を再度いただきました。
附属中学校につきましては、サイエンスフロンティアの精神をしっかりと継続できるように中学校を設置するものであります。この中学校設置が次の高校段階で入ってくる新しい高校生とあいまって、新しいサイエンスフロンティアの精神をしっかり引き継いでいける人材を育成したいという趣旨から、設置するものでございます。以上、ご答弁申し上げました。
