日本共産党横浜市会議員
古谷やすひこブログ
【写真多数】全てが日本からの思いやり予算で作られた、米軍兵が住んでいる住宅はこんな感じです!! ~池子住宅と根岸住宅の視察報告
11月21日(金)晴れ。
今日は横浜市会基地対策特別委員会の市内米軍施設の視察日。
まずは、逗子市と横浜市にまたがっている池子米軍住宅へ。
周りは深い林に囲まれていて、生活環境としてはいいところです。
 これは高層型の住宅。建物一つ一つに、日本の地名の名前がついていて、京都タワーとか、奈良タワーとか、宮島タワーとか。
これは高層型の住宅。建物一つ一つに、日本の地名の名前がついていて、京都タワーとか、奈良タワーとか、宮島タワーとか。
 低層型は、二階建ての建物が横に5~6軒つながっていて、長屋のような感じ。
低層型は、二階建ての建物が横に5~6軒つながっていて、長屋のような感じ。
 中に入ると、もちろん土足で入る。キッチンはこんな感じで、すべて備え付けられています。
中に入ると、もちろん土足で入る。キッチンはこんな感じで、すべて備え付けられています。
 これはリビング。
これはリビング。
 二階には3つの寝室と、そのうち二つにバス・トイレがついています。
二階には3つの寝室と、そのうち二つにバス・トイレがついています。


住宅だけでなく、付帯施設も一通りあります。
これは幼稚園。
 グラウンド。
グラウンド。
 体育館。
体育館。

写真は撮れませんでしたが、最近小学校もリニューアルオープンしたようです。
今度は、池子地域から根岸住宅地区へ。
個々は写真は撮れませんでしたが、広々した芝生が広がる中に、平屋のアメリカ風の家が点在しています。しかしよく見ると、カーテンもなく住んでいる形跡のない家の方が多く見受けられます。
ここは、もはや有名になった根岸住宅地区内にある非提供地域の佐治さんのお宅。
 ここは根岸住宅内にあるショッピングモールのような感じの所。
ここは根岸住宅内にあるショッピングモールのような感じの所。


これらの全ての施設は、日本からの思いやり予算という名の税金が注ぎ込まれいます。さらに言えば、ほとんど居住者もいない施設は速やかに返すのがルールのはず。そのうえ、池子では新たに、171戸の住宅が新たにこれから建設されようとしています。こんなことを本当に認めていいんでしょうか?
中学校給食の検討を迫る!!市教育長への申し入れ ~本日(11/21)付け、しんぶん赤旗の第四面に、昨日の申し入れが掲載されました
本日(11/21)付け、しんぶん赤旗の第四面に、昨日の申し入れが掲載されました。

横浜ぜんそく患者の救済をめざす会が結成されました ~本日付け(11月12日)しんぶん赤旗の首都圏版に、私のことが記事に掲載されました
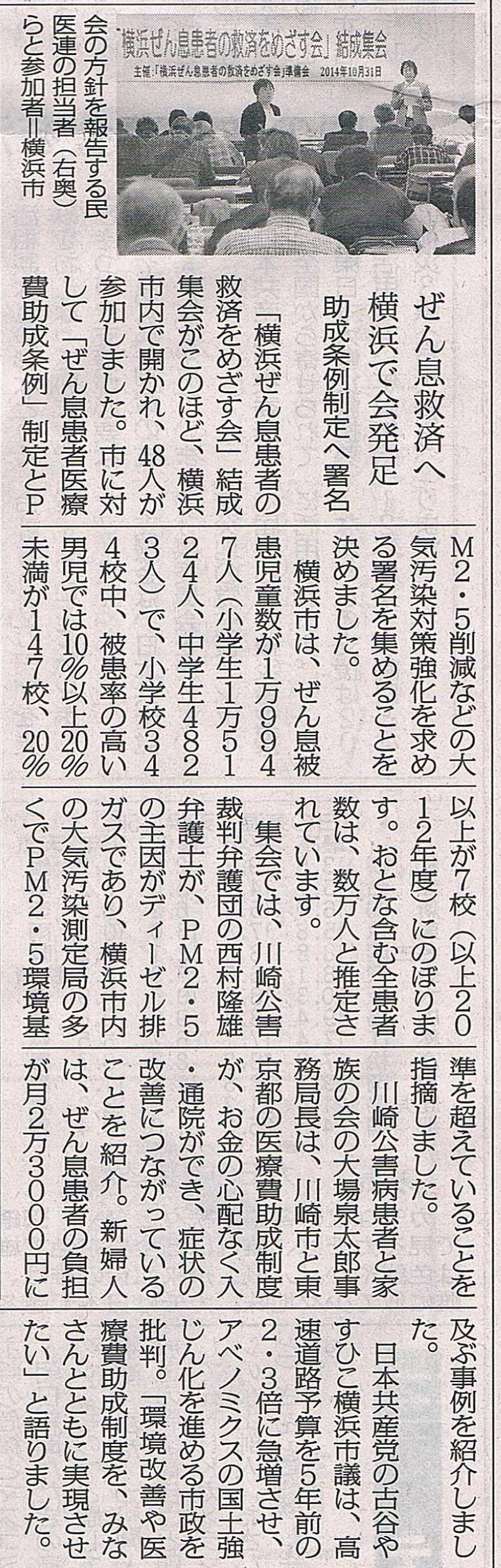 本日付け(11月12日)しんぶん赤旗の首都圏版に、私のことが記事に掲載されました。
本日付け(11月12日)しんぶん赤旗の首都圏版に、私のことが記事に掲載されました。
平成26年度予算特別委員会 予算第一特別委員会局別審査(教育委員会関係)
(2014.3.7)
横浜の中学校では家庭弁当が給食より良いと言い切れるのか
古谷議員:最初にスライドの許可、お願いいたします。
日本共産党、古谷やすひこです。学校給食法に基づいた中学校給食の実施を求めて、質問をしてまいります。本市の中学校で給食を実施していない理由、何か、伺います。
岡田教育長:小学生から中学生への成長を踏まえ、中学校では弁当を基本としております。昭和31年に学校給食法が改正され、中学校でも給食実施が可能になりました。しかし、本市におきましては、昭和30年代後半から40年代は急激な人口増加があり、それに伴って児童・生徒のための授業を行う教室等の整備を中心に学校を建設してきました。その間、家庭弁当が定着し、日本の食糧事情や食生活も大きく改善されたため、優先される課題とはなりませんでした。
古谷議員:では、家庭弁当がいいというふうにおっしゃられているんですが、家庭弁当の良さはなんですか。
岡田教育長:家庭弁当は作ってくれる人と食べる人とがつながりが非常にいいこと、それから自分ならではの良さがその中にあること、そして作ってくださる方との会話や保護者への感謝の気持ちが生まれるきっかけになります。また、アレルギー等の心配がほとんどないことも良さのひとつと考えています。
古谷議員:今ペーパー読み上げられたんですが、そうおっしゃられる裏付けの家庭の調査、やられていますか。
岡田教育長:家庭の調査はしておりません。
古谷議員:そしたら、なぜ、そう言い切れるんですか。
岡田教育長:一般論として、そして私の所感として申し上げました。
古谷議員:教育長が今おっしゃられたようないい面もあると思います。しかし、そういうお弁当作れないという家庭もあるというふうに思います。いろんな家庭があるからこそ、公の役割として成長期に必要な食物を摂取できるように学校給食があるというふうに私は考えますが、教育長の考えを伺います。
岡田教育長:中学生になるという成長段階を考えますと、ご自分で作ることも可能ですし、時間、食材、金額、体調、栄養等さまざまな条件の中で、自分にとってよいと考える食を考えるということはとても大事なことだと思いますし、食生活の形式や食への自立というものも、中学生にとっては、私は大変大切なことだと考えています。
古谷議員:ではなぜ、小学校では給食を選択しているのか、伺います。
岡田教育長:本市におきましては、小学校では学校給食法が施行される以前から小学校において学校給食が実施されており、学校給食法の施行後はこの法律の実施基準に従って実施しているものです。
古谷議員:続いて、今までの答弁の中で教育長は「給食にもいいところがあります。また、家庭弁当にもいいところがある」というふうにされています。それぞれ、給食の課題、家庭弁当の課題、それぞれ何だと考えられていますか。
岡田教育長:小学生の成長過程を考えますと、暖かいものをみんなで一緒に食べることで学び合うこと、それからもちろん栄養バランスのよいものを食べていくということもありますけれども、何よりも子どもたちが給食を食べていくことで成長していくということが大きいというふうに、給食は思っています。
お弁当の良さというのは、先ほど申し上げましたので。お弁当の課題、それはやはり、中学生の課題ということになりますけれども、朝、保護者が作れなかった場合、自分で作れなかった場合のお弁当の調達ですとか、そういうことになると思いますけども。
学校給食法では中学校期だからこそ給食が必要だと書かれているが
古谷議員:今までのは前置きです。これから、いままでの答弁踏まえて、質問していきたいと思います。
先ほど、教育長は答弁の中で、「中学校期になると成長を踏まえて」というお話がありました。そこでお聞きしたいんですけど、先ほど引かれたように、学校給食法では当初小学校までしか対象でなかった学校給食、中学校まで広げた改正学校給食法には改正の趣旨にこうあります。「個人差が大きくなって心身ともに旺盛な発達段階にあるからこそ、適切な学校給食が実施されることが義務教育の完成を目指す上で重要である」と。中学校期だからこそ、給食が必要だと書かれています。教育長のご見解とは真っ向から反すると思いますが、いかがですか。
岡田教育長:給食法が出来ました年代を考えますと、そういうことだったんだろうなというふうに思います。
古谷議員:今はどうなんですか。
岡田教育長:先ほども申し上げましたけれども、当時と比べて日本の食糧事情や食生活の改善は著しいものがあります。それを踏まえますと、一概に給食がいいというふうな結論にはならないんではないかなっていうふうに考えています。
古谷議員:学校給食が法によって規定された意味は、教育長、何だと考えていますか。
岡田教育長:31年に学校給食法が改定されまして、小学校から中学校も実施可能になりました。いろいろ言われておりますけれども、当時の食材調達やいろんなことを考えますと、給食を選択していた都市もあるし、それぞれの事情により実施しなかった都市もあるということだと思います。
古谷議員:もう少し歯切れのいい答弁お願いします。
栄養バランス的に家庭弁当は学校給食より優れているか
古谷議員:続いて伺います。栄養バランスに着目した場合に、家庭弁当と学校給食、どちらが望ましいと考えますか。
岡田教育長:お弁当を作っている保護者の方に対して失礼になるといけませんので、本当に所感ということになりますけれども。すばらしいお弁当を持参している方もいると思いますし、また今、その1食だけで栄養を取るという概念は今の子どもたちにはないというふうに思いますので、1日1週間トータルな栄養バランスを考えて、そのときに取るものがバランスいいかどうかということに関しては、バランスを欠けるというものもあると思います。
古谷議員:もちろんそうです。学校給食法でも、中学生期で1食で摂取される必要な基準というのが学校給食実施基準の別表、スライド出されてませんけど、実施基準の別表で示されていて、それに基づいて全国の8割の中学校では給食が提供されているわけなんです。ですが、本市では、いままでの答弁では、家庭弁当の方が栄養バランスが望ましいという答弁をずっとされています。それはどういった根拠でいままでされていて、今の答弁との違いが、ぜひ教えていただきたいと思います。
岡田教育長:すいません。ちょっと今、ご質問の意味を考えながら立ちましたけれども、家庭弁当で栄養バランスがあるとかないとかっていうお話を答弁としてした覚えがないので、いつの答弁のことだったのかなというふうに、今考えているんですけれども。お弁当にはお弁当の良さがあるし、小学校の給食には小学校の給食としての意味がある、役割があるっていうことはいままでずっと申し上げてまいりました。
古谷議員:はい、では読み上げましょう。2012年度の私どもの予算要望の中で、「中学校において学校給食法に則った給食を早期に実施すること」という中で、回答の中でこうあります。「子どもたちの体調や栄養バランスに考慮した、個々に応じた昼食のほうが望ましいと考え、中学校における昼食は、家庭からの弁当持参を基本としています」と、こう回答されています。これについてどうですか。
岡田教育長:おそらく、一人ひとりの子どもの成長に応じたお弁当が作れる、用意できるということで、当時答弁あったというふうに思います。
古谷議員:今、示されている学校給食摂取基準、本市の中学校の食育の中ではどうやって位置付けられていますか。
岡田教育長:1食あたりの、これは学校給食の基準だと思いますけれども、食育として中学生の成長過程で必要なものということで、トータルに学んでいます。
古谷議員:本市の中学生の食育の中では、どうやって位置付けられていますか。
岡田教育長:中学校で給食を採用しておりませんので、給食としての標準というのは使っておりません。
古谷議員:これ、なぜあげたかっていうと、この学校給食摂取基準というのは、かなり頻繁に臨時改定を繰り返しています。これ、非常に中学生の体格を考えて、臨時改定をずっと繰り返しているんです。そういったことが、学校給食法ではやられているんですけど、そういったことが横浜市の中学校ではどういうふうに位置付けられてやられていますか。
岡田教育長:何度も同じ回答して申し訳ありませんけれども、給食やっておりませんので、給食の基準というのは、位置付けはございません。
横浜市は国の食育推進基本計画や学校教育法に従わないのか
古谷議員:続いて伺います。2010年に食育基本法が制定されて、それに基づいて国が「食育推進基本計画」を策定しました。その中には、学校の役割として「学校給食の充実」の中に「子どもが食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身に付けることができるよう、学校給食の一層の普及を促進する」とありますが、本市はこの普及の方針には従わないということなんでしょうか。教育長、伺います。
岡田教育長:食育は食育で実施しておりますし、今は給食を位置付けておりませんので、給食法のその箇所については位置付けはありません。
古谷議員:丁寧に答えていただきたいんです。食育基本計画の中で、「学校給食の一層の普及を促進する」とあるんです。これに背いてませんかということなんですが。
岡田教育長:給食を実施している小学校ではきちっと基準は尊重しています。中学校では実施しておりません。
古谷議員:丁寧に答えていただきたいんですが。
続いて伺いますね。給食が行われている小学校ですらですね、給食では全部の食事の6分の1しか管理できないので、食育の推進のためには緊密に家庭と連携してやろうとなっています。ましてや給食を実施していない本市中学校では、小学校にも勝る努力と工夫が必要だというふうに考えます。小学校と同じ事業はおっしゃらなくて結構ですので、小学校以上に中学校で行われている家庭弁当での食育を進めるために努力されていること何か、伺います。
岡田教育長:中学校の学習指導要領には、きちんと学校給食を実施していない学校においての食育に関する指導事項も記載されておりまして、それをきちんと踏まえまして、個に応じた家庭弁当でも、教材として特別活動や技術・家庭科などで取り上げることで、食育にしっかり取り組んでおります。
古谷議員:2004年に学校教育法が改正されて、栄養教諭制度が創設されています。その改正の主旨にはこう書かれています「今回の改正は、児童生徒の食生活の乱れが深刻化する中で、学校における食に関する指導を充実し、児童生徒が望ましい食習慣を身に付けることができるよう、新たに栄養教諭制度を設けるものです。この栄養教諭は、栄養に関する専門性と教育に関する資質を併せ有する教育職員として、その専門性を十分に発揮して、特に学校給食を生きた教材として有効に活用することなどによって、食に関する指導を充実していくことが期待されています」。学校教育法の中でも、学校給食が位置付けられています。横浜市は学校教育法にも反しているのではないですか。
岡田教育長:反しているとは思いません。
古谷議員:少し勉強していただきたいというふうに思うんですが、今までの教育長のご発言は本当に破綻しているというふうに思います。ぜひ求めたいというふうに思います。
平成26年度予算特別委員会 予算第一特別委員会局別審査(健康福祉局関係)
(2014.3.5)
必要な人に必要なサービスが届けられる福祉予算を
まず、健康福祉局予算全体にかかわる点でいくつか質問してまいりたいと思います。
厚生労働省が先月の20日に発表した2013年度全国賃金構造基本統計調査で、一般労働者の平均給与が4年ぶりに前年を下回って29万5700円となりました。賃金の低い中小企業やあるいは雇用やパートタイム労働者が増えて、賃金水準全体が押し下げられたと産経新聞などでも報道されておりました。格差と貧困が拡大して、給与が下がり続けている中で、物価も上がり始め、また消費税も来月には増税が待っています。
昨日の新聞報道などでも、中区では経済的に苦しくて無理心中を図る娘と、そして殺されてしまった母親の事件が報道されていました。報道どおりだとしたら、本当に痛ましいことだというふうに感じます。
そんな社会情勢厳しい中、市民の命と暮らしに大きな責任をもつ健康福祉局の予算編成、低所得で厳しい生活苦にあえいでいる市民生活をしっかりと守る立場で予算編成をしていただきたいですし、社会保障機能としても大変重要な所得の再配分機能、さらに強める必要があるというふうに思いますが、局長の見解、伺います。
岡田健康福祉局長:私ども行政が実施する福祉保健サービスはそれを必要とする方に着実にそのサービスを提供していくという基本的な考え方で実施するものというふうに考えております。たとえば、超高齢社会が進むというような2025年を見据えた課題にも今後しっかりと取り組むということで、安全安心の社会を築いていけば、結果として、先生ご指摘のような課題に応えることができるものというふうに考えております。
古谷議員:続けて、健康福祉局予算というのはいつも年々膨れ上がるというふうにして指摘されていますが、その中で、そもそも老齢人口っていうのはこれから自然に増えていくわけで、費用が増えるのは一定仕方がないものだというふうに感じます。それを、健康福祉局内でなかなかやりくりするような、そういった予算組みの中では、何かの予算を削り続けていかなければならないのではないか、そういった構造になっているんじゃないかなというふうに感じます。これではなかなか市民生活を守る予算にはならないんじゃないかなというふうに感じますが、局長の見解、伺います。
岡田健康福祉局長:健康福祉局の26年度の予算案の一般会計の内容ですけれども、対前年度比でいいますと128億円増えて、これは率にすると3.2%の増の予算案というふうになっております。そういう意味では、必要な施策に対しまして必要な予算は確保できているというふうに考えております。今後もサービスを必要とする方に必要なサービスを提供できるような予算組みをしっかりと取り組んでいきたいというふうに思います。
古谷議員:今後の傾向としてですが、全体予算ではなくて、市民のお一人おひとりの生活がどうなっていくのかという視点でみたときに、これから2025年に向けて、個人の負担やサービス、どうなっていくかというような見解があるかと。見解、伺います。
岡田健康福祉局長:それぞれその社会状況によって違うかとは思いますが、これから高齢化が進んでいく、それもこの都市部では急速に進むというような状況の中では、特に私ども健康福祉局が所管する社会保障費の分野などでいえば、今後も増加が見込まれるということになろうかと思います。
非常に出遅れている小児医療費助成の年齢引き上げを
古谷議員:では、少し個別の分野について伺ってまいります。
まず、小児医療費助成の水準について伺ってまいります。来年度予算では、相変わらず小学1年生までと据え置かれてしまい、他都市より大きな後れを取ってしまっているというふうに私は感じております。本市の小児医療費助成の水準、どう認識されているのか伺います。
本田生活福祉部長:本市を除く政令指定都市19市の通院助成の水準の傾向として、対象年齢でみますと、その上限を小学3年生以上に設定をしておりますのは13市で、全体の約7割と多数を占めております。また、所得制限でみますと、制限を設けていないのは11市で、全体の約6割となります。最も助成水準が高いのは、通院・入院とも中学卒業まで所得制限なく助成をしているさいたま市、静岡市など5市が該当し、一方対象年齢・所得制限とも本市を下回っているのは札幌市と広島市の2市となっております。
古谷議員:非常に横浜市は出遅れているというふうに思いますが、今後どう対応されようとしているのか、伺います。
岡田健康福祉局長:やはり小児医療費助成というのは子どものいる世帯などに対するやはり重要な施策というふうに考えております。しっかりとこういったものについては取り組んでいきたいというふうに思います。
古谷議員:今、局長は大変重要な課題だというふうにおっしゃられたんですが、副市長、ぜひ小児医療費助成水準の引き上げの課題、本市予算の中で非常に優先順位が上げられてないとうふうに感じますが、その点の見解、伺います。
鈴木隆副市長:福祉対策、特に子育て支援策については、さまざまな分野、さまざまな項目、事業があります。切れ目のない子育て世代の充実として、26年度予算案では保育所待機児童解消の継続、放課後児童育成推進など多岐にわたって多額の予算を計上しているわけですが、小児医療費助成制度についても、将来を担う子どもたちが健やかな成長を図るための大切な施策のひとつと、先ほど局長が言われたような認識は持っております。だが、多額な予算を必要とするという事業でもございます。そこで、制度拡充の実施については慎重に見極めるという必要があるというふうに思っています。
古谷議員:ぜひ、優先的にも上げていくべき課題だというふうに感じます。
ヘルパーは足りないのに「ヘルパー増加作戦事業」をやめるのか
古谷議員:続いて、ヘルパーの養成の問題について、伺ってまいります。今回の予算の中で、福祉人材就業支援事業の中で「ヘルパー増加作戦事業」という事業が廃止がされています。本市の現状認識として、一般的に本市で働くヘルパーは充足してるのかしていないのか、どちらか、認識を伺います。
妻鳥高齢健康福祉部長:平成22年度に行いました横浜市高齢者実態調査によりますと、たとえば特別養護老人ホームでは半数以上の事業者が介護職員の採用が困難な状況にある、そういった回答をしています。
古谷議員:そういった状況の中で、なぜこの事業がやめられたのか、伺います。
岡田健康福祉局長:このヘルパー増加作戦事業は、市民の方を対象に、介護に関する資格取得を支援し、資格技術を生かした就職へと結びつけるために、平成21年度から実施して5年間で3000人を超えるヘルパーを養成したという実績がございます。24年度の助成対象者へのアンケートを行ったところ、約9割の方が助成制度がなくても資格を取得をしたというふうに回答しているという現状がございまして、廃止するということによって資格取得者が大幅に減少する可能性は低いのではないかということで、この厳しい財政状況の中で考えますと、この事業を廃止するということを決めたものでございます。
古谷議員:では、ヘルパーさんをこれから増やしていかなきゃならないという認識だと当然思うんですが、それについての課題は何だと考えられていますか。
岡田健康福祉局長:やはりこのヘルパーさんという仕事が、やはり多くの人に認知され、そしてそういう仕事を目指したいということが、やはり底辺を広げる、裾野を広げるということがやはり大事なんだろうということで、啓発などがまずは必要だというふうに思います。加えてということになりますが、なかなかいろいろ事業者さんなどから聞きますと、その賃金の問題などもあるというようなことも聞いておりますので、そういったことが課題であるというふうに思っております。
古谷議員:ぜひその点対応していただきたいというふうに思うんです。
通学通所支援のヘルパーを増やせ
古谷議員:それについて、ヘルパーさんが足りないという問題に関連して、障害のガイドヘルプ事業についてちょっと伺ってまいります。この予算では、通学通所支援が今回の予算組みでは大幅に予算額が減らされていました。これは利用実績に合わせたということなんですが、なぜ実績が減ったのか、その原因について伺います。
杉本障害福祉部長:通学通所については、ガイドヘルパーの対応を25年度から開始しましたけれども、やはり朝同じ時間帯に利用が集中する等によって、なかなかヘルパーの利用がそこで対応できていないという、そういった面がありまして、なかなか実績が伸びていなかったというふうに考えられます。
古谷議員:ヘルパーが足りないということだというふうに思うんですが、これでは制度をつくっても実際は使えないということになります。実績にあわせるばかりでは本当のニーズには応えられないというふうに感じます。真に必要な方々が使えないことということになります。どう解消していくのか、伺います。
杉本障害福祉部長:ヘルパー不足への対応という点でございますけれども、22年度から本市では2万円を上限にガイドヘルパー資格を取得する際の養成研修受講料を助成しており、26年度も引き続き実施する予定でございます。また、通学通所支援の実態把握のため、ヘルパー事業者に対して、この1月下旬から2月にかけましてアンケート調査を行っておりまして、まだ集計中ではございますけれども、この結果も踏まえてヘルパー確保の取り組みについて検討していきたいというふうに考えております。
古谷議員:そこで、もう一つちょっと指摘をしておきたいんですが、通学通所支援について、当然、特別支援学校に通っている児童はいま使えているという、まあ使えているといってもヘルパーが足りなければ使えないわけですが、制度上は使えるということなんですが、普通学校の特別支援級に通われている児童は使えません。この対応の違いはなんでしょうか。これでは障害者は特別支援学校に通うように誘導されているとしか思えません。がんばって普通学校に通っている障害児をなぜ支援しないのか、その理由を伺います。
岡田健康福祉局長:特別支援学校とは違い、比較的自宅から近い場所にある普通校の個別支援学級への通学支援については、これはそういう地域に近いと、自宅から近いというようなこともあって、地域のつながりによる助け合いを基本とした地域のガイドボランティアの利用を想定しているということですので、ガイドヘルパーによるサービスは、いまの時点では想定をしていないということによるものでございます。一方で、このところ、障害の重い方も普通校に通学しているという場合もかなり見受けられるというような状況もあるようでございます。そういうことを考えますと、ガイドボランティアの利用状況等も踏まえながら、より専門性の高いガイドヘルパーによる支援についても、検討していきたいというふうに思います。
古谷議員:私のところに、電動車いすで小学校の普通学校に通われている方からも相談がありました。本当にがんばってがんばって通われています。お父さんお母さん方も大変、今疲弊しています。そんな中で、これはなぜこういう差別なのかというふうに私も訴えられました。ぜひ、この点、検討していただくということなので、早急に検討していただきたいと重ねて要望しておきます。
寝具丸洗い・乾燥事業をなぜやめるのか
古谷議員:続けて、「寝具丸洗い・乾燥事業」という事業が今回の予算では制度が廃止をされました。廃止の理由、伺います。
岡田健康福祉局長:この事業は昭和49年に開始した事業で、開始当時と比べると社会情勢大きく変化したという状況にあります。ベットの普及に伴い、布団の使用は減少する。また、大人用紙おむつや防水シート等の介護用品の普及などによりまして、当事業の登録者数は年々減少を続けているという状況にあります。そのようなことから、事業ニーズは低下しておりまして、また他の手段で代替することも可能と判断したため、25年度をもって事業を終了するということにしたものでございます。
古谷議員:この事業の利用者の実施要項をみてみると、この事業の目的の中に「老衰、心身の障害および傷病などの理由により寝具類の衛生管理が困難な寝たきりの高齢者、障害者およびひとり暮らし高齢者が使用している寝具を丸洗い・乾燥事業を実施することにより、対象者の健康増進と生活環境の改善を図ることを目的とする」とあります。この事業対象とされている寝たきりの高齢者あるいは障害者およびひとり暮らし高齢者っていうのは、増えているのか減っているのか、伺います。
妻鳥高齢健康福祉部長:それぞれの区分ごとの数字ということではここではちょっとお答えできませんけれども、全体として高齢者、要介護高齢者、増えているというふうにいえると思います。
古谷議員:対象は非常に、この要項をみても、私も驚いたんですが、非常に対象としては幅広い、今のニーズに私は逆にあっているんじゃないかなというふうに思ってます。必要な方にこの制度、知らせる努力が必要だというふうに思いますが、この点についてどうやってきたのか、伺います。
妻鳥高齢健康福祉部長:この制度につきましては、区役所でのご相談あるいは地域包括支援センターでのご相談、こういったサービスがあるということについてご紹介をしております。
古谷議員:ですからなかなかわかりづらい仕組みになっているというふうに思います。この事業の実施要綱の中で示されている対象者の中に、「一日の大半が寝たきりの状態であること」あるいは「身体障害者・知的障害者」なども含まれており、大変厳しい生活実態であるということが容易に想像できます。普通よりもより丁寧な対応が必要だと思いますが、制度を廃止するにあたって意向調査・収入状況などの生活実態を認識される調査はされたのかされてないのか、伺います。
妻鳥高齢健康福祉部長:事業終了に先立って、利用者の方への意向調査というのは実施しておりません。利用者の収入状況等でございますけれども、現在のところ把握しておりますのは、利用料金が免除となる生活保護世帯の方が約4人に1人ご利用されているというふうに把握しております。
古谷議員:ほとんど把握されてないという中で廃止されるということが決められようとしています。この制度の代替手段、どうされるというふうに提案されるんですか。
妻鳥高齢健康福祉部長:介護保険や民間のホームヘルプサービスをご利用いただいて、定期的に布団の天日干しやシーツの交換というのを行うことで衛生状態の維持というのは可能と考えております。
古谷議員:ヘルパーさんで対応されるというふうにおっしゃりたいと思うんですが、今ヘルパーの時間というは削減される方向にあります。代替できるとどう検証されたのか、伺います。
妻鳥高齢健康福祉部長:たとえば介護保険の訪問介護、ホームヘルプであれば、自己負担額でいいますと、20分以上45分未満の区分ということでご利用いただいた場合には206円になろうかと思います。45分以上の区分であっても255円というご負担になります。そういった状況の中で、判断をいたしました。
古谷議員:大変厳しい生活実態にある方がこの制度、利用されているというふうに想像できますが、また、満足に自分の意思すら表明もできないような方だというふうにも、私は認識をしています。そういった方から、意向調査もせずに、あるいは生活実態も把握せずに、一方的に制度をやめてしまうというのは、あまりにも乱暴なやり方ではないかというふうに思いますが、局長の見解、伺います。
岡田健康福祉局長:本市の高齢者数は増加しているにもかかわらずということになりますけれども、当事業の登録者数はその逆に減少傾向にあるという状況にあります。さらにホームヘルプサービスや布団乾燥機、クリーニング事業者による同種のサービスなど代替可能と思われる手段がほかにあるというふうに考えますので、当事業の必要性はすでに薄れているというふうに判断して、このたび事業を終了するということを決定したものでございます。
古谷議員:この事業は、決して大きな予算規模の事業ではありません。しかし、健康福祉局だからこそ、こういった厳しい生活実態にある方に丁寧に寄り添って対応をしていただきたいと思ってこの問題を取り上げました。もう一度、ぜひ丁寧に意向調査もやったり、廃止の方も撤回していただきたいということは意見表明しておきたいと思います。
UDタクシーの普及促進を
古谷議員:続いて、UDタクシー(注)について伺ってまいります。なぜ普及が広がらないと考えているのか、伺います。
杉本障害福祉部長:ユニバーサルデザインタクシーは、一般のタクシーよりも高い乗車料金と誤解されて、利用者に敬遠されることや、一般タクシーに比べ燃費が悪く、ランニングコストが高いといった課題があります。ということで導入に躊躇しているというタクシー事業者から聞いております。本市としては、まずは多くの方に利用していただくため、福祉タクシー利用券の送付案内への掲載や、市内の主な病院でのリーフレット配架、横浜駅東口での専用乗り場の設置など、PRに取り組んでおり、今後も周知を進めてまいります。
古谷議員:タクシー会社の善意頼みだけではなくて、広がらない原因、ぜひ取り除いていただいて、対策を打っていただきたいというふうに思います。今後どう改善してどうやって普及をさせていくのか、もう一度考え方、伺います。
杉本障害福祉部長:先ほど申し上げました普及が進まない理由をよくタクシー事業者とご相談させていただきまして、どういったことができるかを含めていろいろと検討させていただきたいと思います。
古谷議員:ぜひ、本市の主体的な努力、要請して質問を終えたいと思います。
(注)UDタクシー:ユニバーサルデザインタクシー。健康な方はもちろんと、足腰の弱い高齢者、車いす使用者、ベビーカー利用の親子連れ、妊娠中の方など、誰もが利用しやすい”みんなにやさしい新しいタクシー車両”。料金は一般タクシーと同じ。福祉タクシーの一種で、ワンボックスカーが使われることが多い。
