日本共産党横浜市会議員
古谷やすひこ子育て・保育
横浜市の小児医療費の無料化助成は拡充しましたが・・・ ~「暮らしとからだ」紙3月号の横浜市政報告
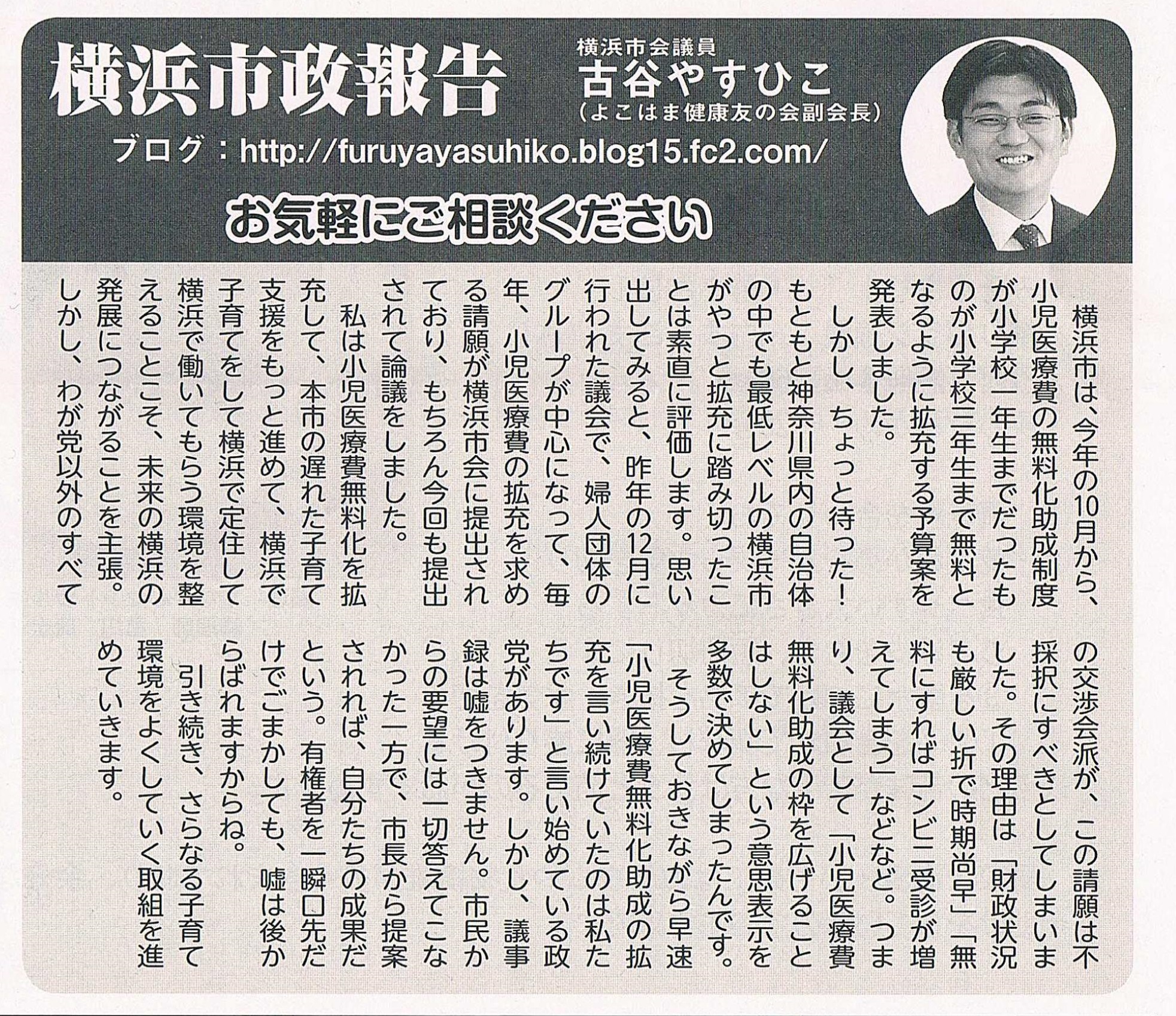
「学校、保育園に保管中の放射能汚染土壌(マイクロスポット対応除去土壌)の回収と市の一元管理を求める要望」を提出しました!
1月30日 金曜日。
今日の予算研究会が始まる前に、副市長に対して申し入れをしてきました。

横浜市内の学校や保育園に保管している放射能汚染土壌が34施設にわたります。その各施設ごとにまかされて保管しているものを、子どもたちが日常的にいる場所から回収して市として一元管理をすることを求めてきました。以下、申し入れ文章です。
2015年1月30日
横浜市長 林 文子様
日本共産党横浜市会議員団 団長 大貫 憲夫
学校、保育園に保管中の放射能汚染土壌(マイクロスポット対応除去土壌)の回収と市の一元管理を求める要望
東京電力福島第一原発事故に由来する放射性物資に汚染された土壌を除去し、敷地内保管していた市立学校20校のうち、4校については、除去目安を下回ったとして、昨年の夏に、保護者に事前周知しないまま、埋設という市の処理方針にもとづき、敷地内に埋設処分としました。保育所、横浜保育室では14施設のうち2施設が、昨年6月に埋設処分です。
議会での追及もあり、学校・保育園における処理方針が、昨年の12月に、見直しされ、除去目安を上回る土壌は、各施設で保管し、除去目安を下回る場合は、従前通り、埋設を基本としながらも、保管を可としました。実質的に埋設方針の撤回です。
党市議団は、今年一月に、港北区、南区の当該の学校、保育園を訪問し、保管状況について調査しました。また、関係者の意見も聴取できました。
保管場所では、不適切な置き場がありました。駐輪場、園庭の一角、校庭の一角など子どもが近づける場所に保管されていました。
 保管方法では、ビニール袋やブルーシートが使われ、仮置き状態の域を出ず、とりあえずの感が否めませんでした。長期保管に耐えられる保管状況とは到底言えませんでした。
保管方法では、ビニール袋やブルーシートが使われ、仮置き状態の域を出ず、とりあえずの感が否めませんでした。長期保管に耐えられる保管状況とは到底言えませんでした。
 敷地内に埋めるという措置については、保護者、周辺住民の理解、教職員の転勤などによる継続性、監視体制など学校や園の対応には限界があることからり、関係者からは、不安の声が多く寄せられました。
敷地内に埋めるという措置については、保護者、周辺住民の理解、教職員の転勤などによる継続性、監視体制など学校や園の対応には限界があることからり、関係者からは、不安の声が多く寄せられました。
こうした事実を総合すると、保管を施設まかせ現場まかせとする現状の方針の問題点が浮かんできます。そもそも、これまで放射能汚染土壌を、再測定で除去目安を下回ったとしても、子どもたちの近くに保管していたこと自体、問題です。今後は、保管方法を厳格にするとはいえ、危険物管理を施設の責任とすることは、施設側だけに負担を押し付けることであり、あまりにも市としては無責任すぎます。市が一元的に放射能汚染土壌を保管する方式に切り替えないかぎり、事態の根本解決は無理です。学校に保管している総量は、約1.7㎥です。計量されていない保育園分を含めても、その量は中型トラック一台の積載分です。一元的管理の技術的隘路はなく、財政負担もほとんどかかりません。市長の決断次第です。
学校、保育園に保管中の放射能汚染土壌について、現行方針を改めて、下記の方針で対処されるよう強く要望し、子どもの安全第一の立場からの市長の決断を求めるものです。
記
1、学校、保育施設が保管している放射能汚染土壌は、回収し、市が一元管理すること。

中学校給食の検討を迫る!!市教育長への申し入れ ~本日(11/21)付け、しんぶん赤旗の第四面に、昨日の申し入れが掲載されました
本日(11/21)付け、しんぶん赤旗の第四面に、昨日の申し入れが掲載されました。

平成26年度予算特別委員会 予算第一特別委員会局別審査(教育委員会関係)
(2014.3.7)
横浜の中学校では家庭弁当が給食より良いと言い切れるのか
古谷議員:最初にスライドの許可、お願いいたします。
日本共産党、古谷やすひこです。学校給食法に基づいた中学校給食の実施を求めて、質問をしてまいります。本市の中学校で給食を実施していない理由、何か、伺います。
岡田教育長:小学生から中学生への成長を踏まえ、中学校では弁当を基本としております。昭和31年に学校給食法が改正され、中学校でも給食実施が可能になりました。しかし、本市におきましては、昭和30年代後半から40年代は急激な人口増加があり、それに伴って児童・生徒のための授業を行う教室等の整備を中心に学校を建設してきました。その間、家庭弁当が定着し、日本の食糧事情や食生活も大きく改善されたため、優先される課題とはなりませんでした。
古谷議員:では、家庭弁当がいいというふうにおっしゃられているんですが、家庭弁当の良さはなんですか。
岡田教育長:家庭弁当は作ってくれる人と食べる人とがつながりが非常にいいこと、それから自分ならではの良さがその中にあること、そして作ってくださる方との会話や保護者への感謝の気持ちが生まれるきっかけになります。また、アレルギー等の心配がほとんどないことも良さのひとつと考えています。
古谷議員:今ペーパー読み上げられたんですが、そうおっしゃられる裏付けの家庭の調査、やられていますか。
岡田教育長:家庭の調査はしておりません。
古谷議員:そしたら、なぜ、そう言い切れるんですか。
岡田教育長:一般論として、そして私の所感として申し上げました。
古谷議員:教育長が今おっしゃられたようないい面もあると思います。しかし、そういうお弁当作れないという家庭もあるというふうに思います。いろんな家庭があるからこそ、公の役割として成長期に必要な食物を摂取できるように学校給食があるというふうに私は考えますが、教育長の考えを伺います。
岡田教育長:中学生になるという成長段階を考えますと、ご自分で作ることも可能ですし、時間、食材、金額、体調、栄養等さまざまな条件の中で、自分にとってよいと考える食を考えるということはとても大事なことだと思いますし、食生活の形式や食への自立というものも、中学生にとっては、私は大変大切なことだと考えています。
古谷議員:ではなぜ、小学校では給食を選択しているのか、伺います。
岡田教育長:本市におきましては、小学校では学校給食法が施行される以前から小学校において学校給食が実施されており、学校給食法の施行後はこの法律の実施基準に従って実施しているものです。
古谷議員:続いて、今までの答弁の中で教育長は「給食にもいいところがあります。また、家庭弁当にもいいところがある」というふうにされています。それぞれ、給食の課題、家庭弁当の課題、それぞれ何だと考えられていますか。
岡田教育長:小学生の成長過程を考えますと、暖かいものをみんなで一緒に食べることで学び合うこと、それからもちろん栄養バランスのよいものを食べていくということもありますけれども、何よりも子どもたちが給食を食べていくことで成長していくということが大きいというふうに、給食は思っています。
お弁当の良さというのは、先ほど申し上げましたので。お弁当の課題、それはやはり、中学生の課題ということになりますけれども、朝、保護者が作れなかった場合、自分で作れなかった場合のお弁当の調達ですとか、そういうことになると思いますけども。
学校給食法では中学校期だからこそ給食が必要だと書かれているが
古谷議員:今までのは前置きです。これから、いままでの答弁踏まえて、質問していきたいと思います。
先ほど、教育長は答弁の中で、「中学校期になると成長を踏まえて」というお話がありました。そこでお聞きしたいんですけど、先ほど引かれたように、学校給食法では当初小学校までしか対象でなかった学校給食、中学校まで広げた改正学校給食法には改正の趣旨にこうあります。「個人差が大きくなって心身ともに旺盛な発達段階にあるからこそ、適切な学校給食が実施されることが義務教育の完成を目指す上で重要である」と。中学校期だからこそ、給食が必要だと書かれています。教育長のご見解とは真っ向から反すると思いますが、いかがですか。
岡田教育長:給食法が出来ました年代を考えますと、そういうことだったんだろうなというふうに思います。
古谷議員:今はどうなんですか。
岡田教育長:先ほども申し上げましたけれども、当時と比べて日本の食糧事情や食生活の改善は著しいものがあります。それを踏まえますと、一概に給食がいいというふうな結論にはならないんではないかなっていうふうに考えています。
古谷議員:学校給食が法によって規定された意味は、教育長、何だと考えていますか。
岡田教育長:31年に学校給食法が改定されまして、小学校から中学校も実施可能になりました。いろいろ言われておりますけれども、当時の食材調達やいろんなことを考えますと、給食を選択していた都市もあるし、それぞれの事情により実施しなかった都市もあるということだと思います。
古谷議員:もう少し歯切れのいい答弁お願いします。
栄養バランス的に家庭弁当は学校給食より優れているか
古谷議員:続いて伺います。栄養バランスに着目した場合に、家庭弁当と学校給食、どちらが望ましいと考えますか。
岡田教育長:お弁当を作っている保護者の方に対して失礼になるといけませんので、本当に所感ということになりますけれども。すばらしいお弁当を持参している方もいると思いますし、また今、その1食だけで栄養を取るという概念は今の子どもたちにはないというふうに思いますので、1日1週間トータルな栄養バランスを考えて、そのときに取るものがバランスいいかどうかということに関しては、バランスを欠けるというものもあると思います。
古谷議員:もちろんそうです。学校給食法でも、中学生期で1食で摂取される必要な基準というのが学校給食実施基準の別表、スライド出されてませんけど、実施基準の別表で示されていて、それに基づいて全国の8割の中学校では給食が提供されているわけなんです。ですが、本市では、いままでの答弁では、家庭弁当の方が栄養バランスが望ましいという答弁をずっとされています。それはどういった根拠でいままでされていて、今の答弁との違いが、ぜひ教えていただきたいと思います。
岡田教育長:すいません。ちょっと今、ご質問の意味を考えながら立ちましたけれども、家庭弁当で栄養バランスがあるとかないとかっていうお話を答弁としてした覚えがないので、いつの答弁のことだったのかなというふうに、今考えているんですけれども。お弁当にはお弁当の良さがあるし、小学校の給食には小学校の給食としての意味がある、役割があるっていうことはいままでずっと申し上げてまいりました。
古谷議員:はい、では読み上げましょう。2012年度の私どもの予算要望の中で、「中学校において学校給食法に則った給食を早期に実施すること」という中で、回答の中でこうあります。「子どもたちの体調や栄養バランスに考慮した、個々に応じた昼食のほうが望ましいと考え、中学校における昼食は、家庭からの弁当持参を基本としています」と、こう回答されています。これについてどうですか。
岡田教育長:おそらく、一人ひとりの子どもの成長に応じたお弁当が作れる、用意できるということで、当時答弁あったというふうに思います。
古谷議員:今、示されている学校給食摂取基準、本市の中学校の食育の中ではどうやって位置付けられていますか。
岡田教育長:1食あたりの、これは学校給食の基準だと思いますけれども、食育として中学生の成長過程で必要なものということで、トータルに学んでいます。
古谷議員:本市の中学生の食育の中では、どうやって位置付けられていますか。
岡田教育長:中学校で給食を採用しておりませんので、給食としての標準というのは使っておりません。
古谷議員:これ、なぜあげたかっていうと、この学校給食摂取基準というのは、かなり頻繁に臨時改定を繰り返しています。これ、非常に中学生の体格を考えて、臨時改定をずっと繰り返しているんです。そういったことが、学校給食法ではやられているんですけど、そういったことが横浜市の中学校ではどういうふうに位置付けられてやられていますか。
岡田教育長:何度も同じ回答して申し訳ありませんけれども、給食やっておりませんので、給食の基準というのは、位置付けはございません。
横浜市は国の食育推進基本計画や学校教育法に従わないのか
古谷議員:続いて伺います。2010年に食育基本法が制定されて、それに基づいて国が「食育推進基本計画」を策定しました。その中には、学校の役割として「学校給食の充実」の中に「子どもが食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身に付けることができるよう、学校給食の一層の普及を促進する」とありますが、本市はこの普及の方針には従わないということなんでしょうか。教育長、伺います。
岡田教育長:食育は食育で実施しておりますし、今は給食を位置付けておりませんので、給食法のその箇所については位置付けはありません。
古谷議員:丁寧に答えていただきたいんです。食育基本計画の中で、「学校給食の一層の普及を促進する」とあるんです。これに背いてませんかということなんですが。
岡田教育長:給食を実施している小学校ではきちっと基準は尊重しています。中学校では実施しておりません。
古谷議員:丁寧に答えていただきたいんですが。
続いて伺いますね。給食が行われている小学校ですらですね、給食では全部の食事の6分の1しか管理できないので、食育の推進のためには緊密に家庭と連携してやろうとなっています。ましてや給食を実施していない本市中学校では、小学校にも勝る努力と工夫が必要だというふうに考えます。小学校と同じ事業はおっしゃらなくて結構ですので、小学校以上に中学校で行われている家庭弁当での食育を進めるために努力されていること何か、伺います。
岡田教育長:中学校の学習指導要領には、きちんと学校給食を実施していない学校においての食育に関する指導事項も記載されておりまして、それをきちんと踏まえまして、個に応じた家庭弁当でも、教材として特別活動や技術・家庭科などで取り上げることで、食育にしっかり取り組んでおります。
古谷議員:2004年に学校教育法が改正されて、栄養教諭制度が創設されています。その改正の主旨にはこう書かれています「今回の改正は、児童生徒の食生活の乱れが深刻化する中で、学校における食に関する指導を充実し、児童生徒が望ましい食習慣を身に付けることができるよう、新たに栄養教諭制度を設けるものです。この栄養教諭は、栄養に関する専門性と教育に関する資質を併せ有する教育職員として、その専門性を十分に発揮して、特に学校給食を生きた教材として有効に活用することなどによって、食に関する指導を充実していくことが期待されています」。学校教育法の中でも、学校給食が位置付けられています。横浜市は学校教育法にも反しているのではないですか。
岡田教育長:反しているとは思いません。
古谷議員:少し勉強していただきたいというふうに思うんですが、今までの教育長のご発言は本当に破綻しているというふうに思います。ぜひ求めたいというふうに思います。
平成25年度決算特別委員会 決算第一特別委員会局別審査(こども青少年局関係)
(2013.10.9)
放課後キッズの17時以降の利用児童はなぜ少ないのか
古谷議員:日本共産党、古谷やすひこです。放課後施策について伺ってまいります。
小学校入学とともに保護者が仕事を辞めざるを得ない、いわゆる『小一の壁』、これは取り除く施策をぜひ進めるべきだと思いますが、局長の見解、伺います。
鯉渕こども青少年局長:小学校就学後の学齢期や子どもが生きる力を育み、調和のとれた発達を図る重要な時期です。小一の壁の打開に向けて、できるだけの対策をとってまいりたいというふうに考えております。
古谷議員:今回、子ども・子育て事業計画案では、放課後事業の量の見込み、2万4,000人とされていますが、これで小一の壁は打開できると思っていますか。
鯉渕こども青少年局長:子ども・子育て支援事業計画案で算定しております放課後児童健全育成事業の量の見込みは、25年度に未就学および小学生の保護者に実施した利用ニーズ把握のための調査の結果に基づいております。なお、未就学期と異なり、小学就学後は、習い事や塾等に通ったり、友人同士で過ごすなど、子どもと保護者の選択により、さまざまな放課後の過ごし方があることが、保育所の利用者に比べると少なくみえる理由のひとつではないかというふうに考えております。
古谷議員:今議会の白井議員の質疑の中で、キッズクラブが17時以降の平均10人しか受け入れていないということについて、市長は「児童が高学年になると習い事をしたりひとりで留守番ができたりすることから、利用頻度が減少する傾向にある」と回答されています。これは実態調査をされた結果なのかどうか、伺います。
鯉渕こども青少年局長:ただいま申し上げたとおり、25年度に実施した子ども・子育て支援事業計画の策定に向けた利用ニーズ把握のための調査において、放課後事業を利用していない小学生の保護者の方に放課後の過ごし方を確認したところ、習い事や学習塾、放課後短時間なら子どもだけで過ごしても大丈夫、祖父母宅や知人・友人宅で過ごせるというような結論が出ております。そうした過ごし方も一定程度あるということで、こうしたニーズが2万4,000という数字になっております。
古谷議員:1年生のキッズの登録数が7,499人と聞いています。17時以降の受け入れが559人ということですから、つまり7,000人近い1年生が17時以降、どういう状況になっているのかというのは把握されていますか。
鯉渕こども青少年局長:何らかのかたちでご自宅にいらっしゃる、または塾等に出かけている、そういったことではないかというふうに思っております。
古谷議員:把握されていないということだと思うんですが。
キッズを全校展開するのであれば、本当に留守家庭対策として機能しているのかどうか検証することが必要だと思います。キッズの登録児童がいま2万6,873人います。17時以降になると、約2万6,000人が帰ってしまう。つまり、97%が17時以降には利用していないということですから、何らかの分析であったり、あ
るいはニーズ調査、これ必要だと思いますが、どうでしょうか。
鯉渕こども青少年局長:現在の計画を立てる上にあたり、ニーズ調査はしております。
古谷議員:細かな実態はつかんでらっしゃらないというふうに思います。
キッズクラブについて、もうひとつ問題があります。全校展開するというのであれば、障害児の対応というのは、これはもう必須だと考えます。個別支援学級に入っている児童だけもいま3,845人います。キッズクラブに登録している障害児数は665人。17時以降の登録数は58人と、がくっと減ってしまいます。この原因について伺います。
鯉渕こども青少年局長:放課後キッズクラブの利用は、障害児を含むすべての子どもの利用状況として、25年度実績では1か所一人あたり平均参加児童数57.4人なんですが、17時以降になりますと平均参加児童数は10.3人となっております。17時以降の利用児童が昼間に比べて少ないという傾向は、障害児のみにみられる傾向ではなく、全般的な傾向となっております。
古谷議員:これは、ぜひ実態つかんでいただきたいと思うんです。キッズの全校展開にあたっては、障害児の受け入れもいま以上の充実強化、必ず必要だと思いますが、いかがでしょうか。
鯉渕こども青少年局長:障害児のいまの動向として、増えている、増加傾向にございまして、すべての対応の中で、障害児の受け入れは推進していく必要があると考えております。
古谷議員:キッズクラブの運営指針の中には人材の確保と養成というふうにありますが、この問題についての課題、どう認識されていますか。
鯉渕こども青少年局長:現在は、新制度への移行の時期でございますので、有資格のある方、研修等でも資格を取ることができるようなかたちになっておりますが、そうした人の確保が重要ではないかというふうに考えております。
古谷議員:キッズが本当に、真に留守家庭児童の放課後の生活の場所となれるように、改めて対策を求めます。
学童クラブの移転分割にもっと踏み込んだ支援を
古谷議員:次に、放課後児童クラブ、いわゆる学童クラブについて伺います。法制化されて基準ができたことは本当に大歓迎します。しかし、それだけでは学童クラブを運営する側にとっては負担が増えるだけというふうになります。面積基準や耐震性の問題で、移転したりあるいは分割しなければならないクラブはどのくらいあって、今後どのように解消しようとしているのか、伺います。
鯉渕こども青少年局長:25年夏に実施した施設実態調査をもとに、その後の状況調査をしておりますが、対象児童を6年生までで算定いたしますと、面積基準を満たしていないクラブは91、それから旧耐震の建物または建築年がわからない耐震化不明のクラブが83ございます。両方とも重複してクラブが36ございますので、合わせて138か所が分割移転が必要というふうに考えています。
古谷議員:今後、どのように解消されようと思っていますか。
鯉渕こども青少年局長:現在も分割移転につきましては整備助成をしておりますが、区と局とが一体になりまして、そうした対応をしてまいりたいというふうに考えております。
古谷議員:いまの制度でなかなか解消できていないというふうに思うんですが、そこ、なぜ進んでいないと思いますか。
鯉渕こども青少年局長:面積を満たす場所を見出すということも必要なことでございますし、さらに放課後児童クラブとなりますと子どもたちが元気ですから、そうしたことを受け入れていただける周辺というんでしょうか、そういったことも重要ではないかというふうに考えております。
古谷議員:自助努力ではどうにもならない学童クラブもあるというふうに思います。それに対して、行政としての支援も必ず必要だと思いますが、どうでしょうか。
鯉渕こども青少年局長:現在、物件の確保策といたしまして、不動産関係団体と協力して物件情報を市ホームページ上で公開するとともに、新聞広告等も活用して空き物件の募集情報掲載なども行ってきておりますが、今後地域情報に詳しい区とともに、関係局と協力しながら、物件の確保に努めてまいりたいと考えております。
古谷議員:実際、学童の現場で、いまのキッズの全校展開の問題、あるいは金銭的な問題、あるいは指導員の確保の問題、こういった問題で、なかなか分割移転に踏み切れないというのが現場の状況だというふうに思っています。もっと踏み込んだ支援を、ぜひ現場に近い区役所にもしっかり担当者をおいて、増員して対応すべきだと思いますが、どうでしょうか。
鯉渕こども青少年局長:おっしゃる趣旨もわかりますので、保育所待機児童対策のノウハウなども生かしながら、地域情報が得やすい区と協力してまいりたいというふうに考えております。
放課後キッズの3倍の学童クラブの利用料にもっと公的補助を
古谷議員:キッズの利用料金5,000円と比べると、いまだいたい学童クラブは約3倍の利用料金が必要です。同じ放課後児童対策であるのに、あまりにも格差が大きく、これは是正するなり、市の助成金を増やすなり、何らかの対応が必要だと思いますがどうでしょうか。
鯉渕こども青少年局長:放課後キッズクラブは保護者の就労にかかわらず、すべての子どもたちの遊びの場としての役割がございます。その役割である17時まで時間帯につきまして、国の考え方として、実費を除き利用者負担を求めないということになっております。一方、放課後児童クラブは留守家庭の子どものための事業でして、国の補助金交付上の考えとしても、運営費の2分の1は保護者負担ということが示されております。こうした考え方をもとに利用者負担が設定されております結果ということでございます。
古谷議員:ひとり親であるとか多子減免、いまはそれぞれの学童クラブで自主努力の範疇でやっていますが、本来は、市民税非課税と同様に公的減免とするべきだと思いますが、どうでしょうか。
鯉渕こども青少年局長:ひとり親家庭、多子減免につきましては、いま今回の放課後事業につきましては新しい制度の中で動きがあるタイミングでございます。国の動向をみながら検討してまいりたいと思います。
古谷議員:これから、先ほど述べられておる138か所の学童クラブの分割移転をするためには、指導員の確保をしなければならないとしたときに、現状の指導員の処遇、必ず改善することは待ったなしの課題だと思いますが、どうでしょうか。
鯉渕こども青少年局長:現在でも、本市は国の補助基準額を上回る運営補助をしております。今後の助成の内容につきましては、消費税が10%になるという前提での国の方の検討内容でございますが、新制度移行の中で、処遇改善的な質の改善を検討するということになっております。そうした動向を見極めてまいりたいと考えております。
古谷議員:キッズクラブがさらに質を高めることと、学童クラブが法制化されたことで、今まで学童が要望し続けてきた一歩踏み込んだ公的支援、ぜひ行うことを、本市の留守家庭児童対策を先進的なものに、ぜひ、していただくよう要望して、質問を終えます。
