日本共産党横浜市会議員
古谷やすひこ道路・交通
【拡散願います】IC化された敬老パスでSuicaから引かれてしまった、という方へ。
10月からスタートした敬老パスのIC化ですが、いくつか問題が寄せられています。
「ICカードを出したのに、Suicaなどから引かれてしまった・・・」というもの。
敬老パスを担当している健康福祉局の担当者に聞いていみると、
「確かにそういう苦情はあります。間違って仮にSuicaで引かれた場合、その引かれた交通事業者にその場で言えば、何らかの対応はしてくれると思いますが、市としてそれを言うこともできないので…。」と
私からは
「せめて、そういう場合はすぐに交通事業者に相談してほしいと書いてはどうか。」と要望。
敬老パスの仕組みでは、読み取り機に敬老パスのICカードとSuica等を一緒にかざしても、Suicaから引かれることはないようです。しかし、その敬老パスの読み取り機が見えづらいところにあると、Suicaなどの読み取り面に一緒にかざしたSuicaが引かれてしまう、というもの。
ちなみに、市営バスにはこういうところに設置してあるそうです。


慣れるまでは少し大変かもしれません。
とにかく間違ったと思ったときに、すぐに伝える対応が必要かと思います。
「舗装の凸凹で母親が転んでしまった。なんとかして!!」との相談が・・・ ⇒ 速やかに改善を実現!!
5月の連休前に、相談が入りました。
「近所の踏切の直前の舗装がボコボコの状態で、車輪付きの杖で母親が先頭に出かけたときに、舗装の陥没部分に車輪を取られ転倒した。車が並走していたらと思うとぞっとします。なんとかならないでしょうか?」とのメール。そして一緒に送られてきた写真が以下の通り。

早速、鶴見土木事務所と相談して、現場を確認してもらうと、「これはなかなかひどいですね。すぐに対応します!」と早期対応を約束してくれました。

みなさんの周りでも、何か気づいたことや改善してほしいことがありましたから、連絡ください。すぐに対応します!
街灯がつかないつかないことを相談するのはどこに!? ~「暮らしとからだ」2016年11月号に掲載されました
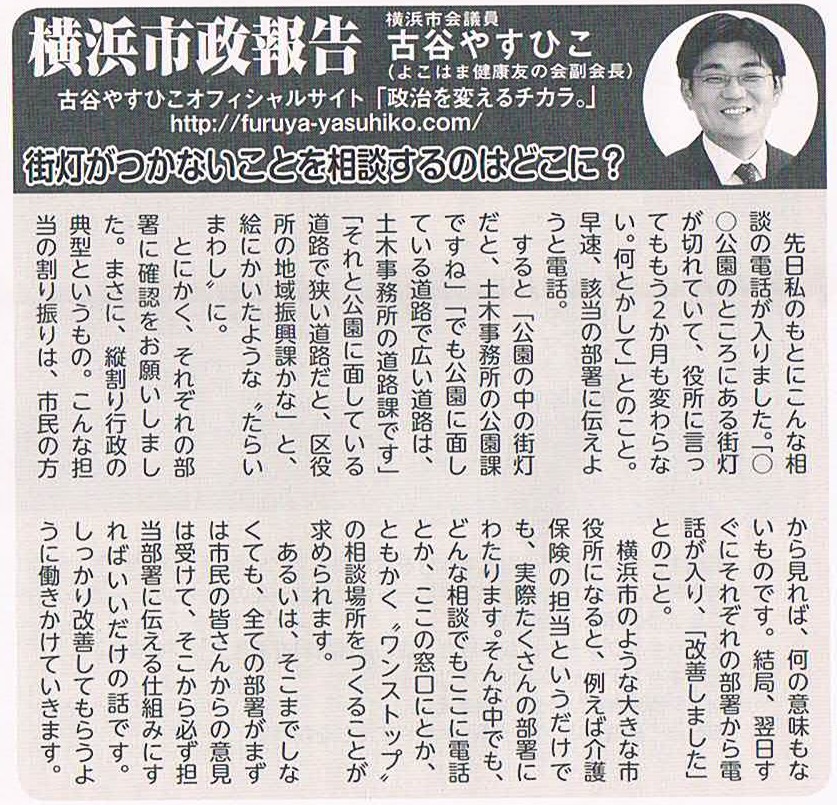
鶴見区の地元問題である「生見尾踏切に、エレベーター設置を早く」 ~横浜市会本会議(9/9)で林市長に私が求めたこと その五
生見尾踏切に、エレベーター設置を早く

古谷議員:
最後に、鶴見区の生見尾踏切のエレベーター付き跨線橋の未設置の問題についてです。
生見尾踏切では死亡事故が起きて丸3年。市長はすぐに跨線橋を設置すると言いながら、いまだに設置がされていません。それは、踏切を閉鎖してエレベーター付き跨線橋を付けるという横浜市の提案が地元の自治会や商店街のみなさんにまったく納得されていないためであります。
そもそも、何のために誰のために跨線橋をつけるのかと言えば、地元のみなさんが安全に線路をわたれるようにするためであります。しかし、いくら安全にといっても、地元の猛反対を押しのけて踏切閉鎖を強行し、跨線橋を設置しても、地域が分断されたと地元に遺恨が残るだけであります。
踏切廃止ありきの横浜市の提案に固執して結論を先延ばしするのではなく、まずは地元との間で合意ができている交通弱者のためのエレベーターの早期設置すべきと思いますが、どうか伺って、一旦質問を終えます。

林市長:
生見尾踏切について、ご質問いただきました。
踏切を閉鎖せず、エレベーターの設置を早く進め、地元の意向をしっかりと国に伝えるべきとのことでございますが、生見尾踏切は横浜市が定めた踏切安全対策実施計画において抜本対策が必要な踏切と位置付けています。また、3月に開設された踏切道改良促進法に基づき、今後抜本対策が必要な踏切に指定されると考えられます。このため、生見尾踏切の安全対策としては、大型のエレベーターを併設し、すべての歩行者および自転車が利用できる規模の跨線人道橋を整備する必要があると考えています。
[都市計画道路岸谷線]64年前に策定された計画を粛々と進めようとしている横浜市の道路行政の不思議!?「なぜ事業見直ししないのか???」 ~計画をすすめれば、立ち退き対象が130軒以上、全路線買収率も一割以下
今から64年前のこと。とある道路計画が、都市計画決定されました。
それは、都市計画道路岸谷線(1952年7月16日)。
しかし計画当初から沿線住民を中心に大反対運動がおこり、今でも毎月「都市計画道路岸谷線と大気汚染を考える会」の役員会が行われ、計画路線を実際に見てみる「岸谷線ウォッチング」や、岸谷線の計画の現状を伝える住民説明会を二か所で開催する等、活発な岸谷線反対の活動が繰り広げられています。
今日は、その会の役員さんたちが勢ぞろいして、6月に行われる住民説明会に向けて、要望項目の提出と説明会への出席を求めて、市の道路局の担当者と懇談をおこない、その場に同席しました。
「このままの岸谷線計画を進めるとうちの町(柳町)がなくなってしまう。」
「ぜひ現場を実際に見ていただいたうえで回答をいただきたい。」
など、直接役員さんたちが市の担当者に訴えました。
そもそもこの岸谷線の計画は、64年前に策定された計画で、このままの計画が実施されれば、立ち退きの対象となる家が130軒、先行して買収されている土地が4000㎡ 約27億円で、全路線の一割以下の買収率。
とても現実的な計画とは思えません。速やかに計画の撤回を求めていきます。

