日本共産党横浜市会議員
古谷やすひこ視察・研修
あのテレビドラマの舞台にもなった横浜市立盲特別支援学校へ視察に行ってきました!
横浜で唯一の「横浜市立盲特別支援学校」に、北谷議員と一緒に視察に伺いました。
![IMG_6579[1]](http://furuya-yasuhiko.com/wp-content/uploads/IMG_65791-400x300.jpg)
日本で3番目にできた盲学校。もともと私立だったものを市に移管して現在に至ります。
少し前にやっていたテレビドラマ「恋です! ヤンキー君と白状ガール」の舞台にもなった学校。
![IMG_6573[1]](http://furuya-yasuhiko.com/wp-content/uploads/IMG_65731-400x300.jpg)
横浜市立でありながら、市外からの生徒の受け入れも行っており、現在市外から通っているのは2割とのこと。
現在、幼稚部から高等部まで、76人が在籍しています。写真は、幼稚部のプレイヤード。
![IMG_6546[1]](http://furuya-yasuhiko.com/wp-content/uploads/IMG_65461-400x300.jpg)
今回の視察では、登校の様子も見させてほしいとして、白状を使いながら自力で登校する高等部生。そのために最寄りの駅からはずっと点字ブロックがつながっています。降雪した際は、大変で教職員はもちろんのこと近所の方も総出で点字ブロックの雪を取り除くんだそうです。歩行訓練士の資格を持った教員は3名いるそうです。
保護者が自家用車で送ってくることもありましたが、ほとんどは、二方向からくるスクールバス。スクールバスで学校についてから、一人一人を安全に教室まで送り出しているのは、教職員の総出で行っています。
給食は、幼稚部から高等部まで自校方式での給食が提供されています。
![IMG_6572[1]](http://furuya-yasuhiko.com/wp-content/uploads/IMG_65721-400x300.jpg)
全体としては、通常の学校での受け入れを進めるインクルーシブ教育が進められる中、盲特別支援学校を希望する児童生徒は減少傾向。しかし、弱視や盲の生徒がいる学校への支援を行うことも、この学校の役割だそうです。
体育館やプールなどももちろん完備しています。
![IMG_6556[1]](http://furuya-yasuhiko.com/wp-content/uploads/IMG_65561-400x300.jpg)
![IMG_6548[1]](http://furuya-yasuhiko.com/wp-content/uploads/IMG_65481-400x300.jpg)
中でも、ここの図書室が素晴らしい。単なる学校の図書室というだけではなく、点字図書館としての機能が充実しています。
![IMG_6559[1]](http://furuya-yasuhiko.com/wp-content/uploads/IMG_65591-400x300.jpg)
![IMG_6560[1]](http://furuya-yasuhiko.com/wp-content/uploads/IMG_65601-400x300.jpg)
この運営にはたくさんのボランティア団体が関わっていただいています。
![IMG_6570[1]](http://furuya-yasuhiko.com/wp-content/uploads/IMG_65701-400x300.jpg)
これが拡大読書器。
![IMG_6562[1]](http://furuya-yasuhiko.com/wp-content/uploads/IMG_65621-400x300.jpg)
こういう専門の特別支援学校の役割は、まだまだ横浜市にとって本当に大きいものがあります。
視覚障害者にとっては命綱のような存在であるし、またそういう役割を果たしていかないといけないと思います。
今後、教員の育成の問題、遠くから通ってこないといけない子どもたちへの支援の問題などなど、解決しなければならないことを
一歩ずつ改善させていきたいと思います。
[現場写真多数] 放射能に汚染された「指定廃棄物」を学校現場に置く必然性はありません! ~横浜市と国に対応の改善を求めます!
現在、横浜市内の43の小学校・中学校・特別支援学校で、放射性物質に汚染された汚泥が校内に保管されています。その量、2908.8㎏、ドラム缶で87本だとのこと。

その中には、8000ベクレルを超える「指定廃棄物」も含まれています。これは、放射性物質汚染対処特措法に基づいて横浜市が国に申請し国が指定しました。その国による指定廃棄物は、上記のうち、17の学校でその総量は3トンに及びます。
そのうち、もっとも多量の832㎏の指定廃棄物を保管している末吉小学校の現場がこちら。左側に並んでいるのが指定廃棄物の入ったドラム缶。

この指定廃棄物は「消火ポンプ室」に、ドラム缶5本の中に保管されています。横浜市が立ち会い環境省が計測した数値は、11300ベクレル(2013年10月に公表したもの)。8000ベクレルをはるかに超えています。
![IMG_4523[1]](http://furuya-yasuhiko.com/wp-content/uploads/IMG_45231-400x300.jpg)
私が持参したHORIBA Radi PA-1000で空間線量を測ってみましたが、ポンプ室内では0.10~0.15マイクロシーベルト/h。ドラム缶に機械を置いても、大体変わらない数値。
(環境省で測定した結果の資料を現在請求しています。)
![IMG_4522[1]](http://furuya-yasuhiko.com/wp-content/uploads/IMG_45221-e1460032486164-300x400.jpg)
![IMG_4524[1]](http://furuya-yasuhiko.com/wp-content/uploads/IMG_45241-e1460032547382-300x400.jpg)
もう一か所は、13200ベクレルで63.2㎏の指定廃棄物が保管されている下野谷小学校の現場を視察。「雨水ポンプ室 消火ポンプ室」に保管されています。その入り口には、雨水利用設備の説明版があります。皮肉にも、この仕組みを導入したために、横浜に降り注いだ放射性物質をわざわざ集積することになったんです。
![IMG_4533[1]](http://furuya-yasuhiko.com/wp-content/uploads/IMG_45331.jpg)
どちらの現場も、確かに基本的には子どもたちが立ち寄らない場所で保管されていることは確認できました。
しかし、やはりわざわざ子どもたちの日常生活を過ごすところに置き続ける意味はないと思います。また、いつ災害が起こるかもしれません。火事になるか、地震や水害が起こる可能性は、東日本大震災で私たちはもう経験しています。いつどんな災害が起こってもおかしくありません。そういう来たるべき大災害に備えて様々な備えをしている中で、わざわざリスクのあるものを避難所にもなる学校に置き続ける意味はありません。
「移動する場所がない」というのも、全くナンセンスで、場所はあります。残念ながら現在でも、北部と南部の汚泥資源化センターで放射能汚染された汚泥焼却灰が積み上げられています(2年前の視察の際の様子)。

それらをそこの置き続けることが適切であるというつもりはありませんが、少なくとも子どもたちのいる小学校・中学校に今置いておくよりも、そこに指定廃棄物でないものも含めて全部合わせても3トン程度ですから、北部と南部の汚泥資源化センターで保管されている下水汚泥焼却灰と同様に保管するように、速やかに移動させるべきです。
しかし横浜市は「事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理等についての対応」という文章の中で「廃棄物の保管については、引き続き施設管理者が施設内で適切に行うことを原則とする。また、調整後、指定申請を行った廃棄物についても、国に引き渡すまでの間、適切に保管する」として、学校に指定廃棄物を置き続けることの方針を変えていません。
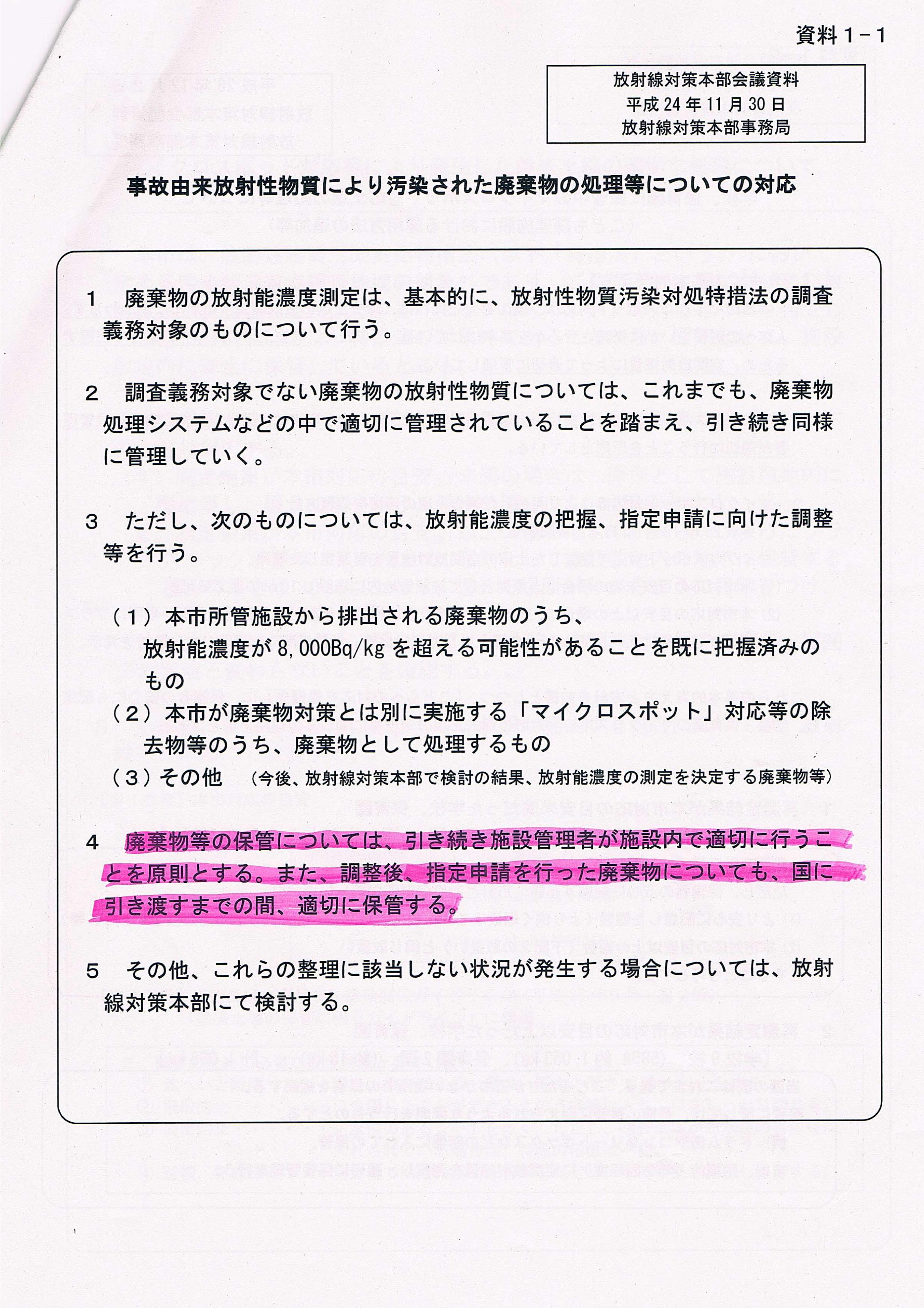
教育現場をあずかる担当者もこんなお荷物を管理するのは本意であるはずがありません。
引き続き、横浜市に対して働きかけ続けるとともに、次は国に対して、指定廃棄物を引き取るように求めて、来週の金曜日に環境省へと行ってきます。
環境省のホームページには、「国による処理体制が整うまでの間、やむを得ず一時的な保管をお願いせざるを得ない状況が続いています」とあります。一時保管だと言いながら、5年も、そしてわざわざ子どもたちのいる学校に指定廃棄物を置き続けるのは、あり得ません。即刻改善を求めていきます。
「『介護保険制度ではない』『特養』ではない、養護老人ホームを知っていますか!?」 ~養護老人ホーム「野庭風の丘」の視察報告
養護老人ホームを知っていますか?
「老人ホーム」でも「特養」でもありません。
老人福祉法の第十一条に「市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。」その一項に「六十五歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。」とあります。
介護保険制度がはじまり高齢者福祉サービスは、基本的に契約による利用形態となりました。しかし、介護保険法施行後もさきの老人福祉法において、家族の虐待等により、 介護保険サービスの利用や居宅において養護を受けることが困難な高齢者に対し、市町村が職権をもって必要なサービスを提供するために措置制度が存続しています。
では具体的にどういう人が入所するのか?
○原則として65歳以上で環境上の事情や経済的事情があり、居宅に置いて養護を受けることが困難である場合。但し入院加療が必要でないもの。
○環境上の事情とは、家庭や住居の状況など、現在置かれている環境下では在宅に置いて生活することが困難である場合。
○経済的事情とは、低所得(市民税所得割非課税など)世帯の高齢者
こういう養護老人ホームが、横浜市内に6か所あります。その一つの港南区にある「養護老人ホーム 野庭風の丘」に、みわ議員と一緒に視察に行ってきました。

ここは120人の定員の施設ですが、現在入所しているのは6割程度。空きが目立ちます。居室は個室のみ。

一日三食、この食堂で手づくりのご飯が食べられます。

お風呂は、7~8人が同時に入れます。

その他、地域に開放しているホールや会議室、また屋上庭園等の施設もあり、充実しています。
その後、施設長や市の担当者との懇談。
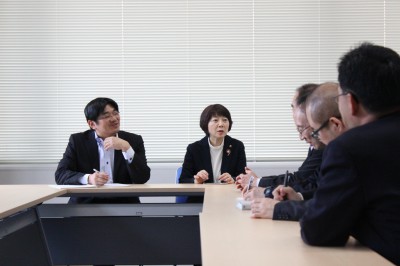
最近、入所してくる方の傾向は?
「やっぱりDVの方ですね。アルコールや精神疾患などの方も多いですね。」
費用は?
「39階層に分かれていて、0円から14万円まで。平均で言えば、54000円程度だと思います。」
介護保険制度が徐々に制度改悪で形骸化されつつある中、その介護保険制度をめぐるたたかいだけではなく、従来地方自治体が担っていた老人福祉の制度を充実させることも必要です。
今回の養護老人ホームなどはその最たるものです。
市に対しては、ニーズ量調査を改めて行うことを求めて、それに基づき養護老人ホームの必要量を増設すること、を求めます。
また、国には、市町村が養護老人ホーム増設を促進させるような施策を打つことを求めていきます。
横浜で唯一の美術館「横浜美術館」の改修こそ、前倒しをしてでも優先順位高く行うべき!!
先日、下記の新聞記事を目にして、早速北谷議員と現場の横浜美術館へ視察に行ってきました。

早速、いくつかのポイントを担当の方に案内してもらいながら、ヒアリング開始。
まずは、来年度の改修予定で、先ほど確定した来年度予算によれば1億7500万円ついているものの内訳は、
まだ和式のトイレが大半を占めているので、そのトイレの改修に2000万円。
また、自動火災報知機の全面取り替えに1億円。
電源の改修に、4000万円。
その他プラスα。
確かにトイレは、和式がほとんどで洋式トイレは一か所のトイレに一つしかない。

また、西入口付近の路面が割れているのを改修するとのこと。

収蔵庫なども見せてもらいましたが、厳重なセキュリティーの中には、確かにたくさんの収蔵品がありましたが、もう入る余地がないわけではない。
今後、増え続ける収蔵品をどうしていくのを検討している最中とのこと。
来年度には、老朽化への対応や収蔵庫の拡張の問題などを含めた全体的な基本設計に着手し、最短では4年後に改修工事を開始するとのこと。
その総金額は、数十億から100億円の間というもの。
結局、東京オリンピック・パラリンピックの開催には、「大規模改修に取り組むと年単位で閉館状態にならざるを得ないこと」「事業費が高騰するため」改修は行わないということ。
今回の視察を経て、こういう本市で唯一の美術館の改修は前倒しをしてでも行うことこそ、文化の香りかおる横浜には相応しいお金の使い方ではないかと思う。
先ほどの理由で、美術館の改修は後回しにする一方、横浜環状道路北西線や山下埠頭の第一期工事、新市庁舎などの大型開発については、「東京オリンピック・パラリンピックまでに」と言っているのは、ご都合主義に聞こえてしまう。
横浜美術館改修、計画5年遅れに 進む老朽化/満杯迫る収蔵品
 |
完成から二十七年が過ぎ老朽化が懸念される横浜美術館(横浜市西区)=写真=の大規模改修計画が、当初の想定より五年ほど遅れていることが市などへの取材で分かった。二〇二〇年東京五輪に間に合わせるため一九年度までに工事を終える予定だったが、他の施設の改修を優先したという。美術品の収蔵・収集などに影響が出る可能性があるが、市は計画の遅れを公表していない。 (志村彰太)
横浜美術館は一九八九年の横浜博覧会に合わせ、みなとみらい地区に開館した。建物は鉄筋コンクリート八階建てで、日欧の近現代芸術作品を収集、紹介している。一四年度の入館者数は五十三万人。
外見上はきれいな現代建築だが、市文化振興課は「不具合も出てきている」と話す。四~七階の収蔵庫は満杯に近づき、拡張が必要。収蔵できる限界量を市は試算していないが、近年では毎年三百点ほど収蔵数を増やし、昨年は計一万一千点を超えた。
美術品の適切な保存に欠かせない空調設備は、交換の目安となる設置後三十年が近づいている。トイレは同時に多くの人が使うと詰まり、敷地内の地面はうねりが発生している。
大規模改修では、これらの課題や不具合を全て解決する予定だった。
市はもともと、「一五年度から改修の検討作業に着手し、一八年度から工事。その翌年度に完了する」とする検討資料を作成。一四年度に修繕の必要箇所を洗い出す調査で「数十億~百億円かかる」と試算していた。
ところが、昨年三月、公共施設を管理する市営繕企画課と文化振興課の話し合いで、「美術館より古い関内ホール(八六年完成)の改修を優先すべきだ」と指摘があった。このため、美術館の後に取り掛かる予定だった関内ホールと優先順位を変更した。
変更後の計画では、関内ホールを一六~一八年度に改修した後、美術館の改修に取りかかる。東京五輪前で建築資材や人件費の高騰が予想されるこの時期を避けるため、着手は二一年度以降までずれ込む見通しだ。文化振興課は「東京五輪や横浜トリエンナーレに間に合わせようとしたが、五年は遅れる」と話す。
文化振興課は「内部での検討にすぎず、公表の必要はない」と説明するが、計画は一四年度の包括外部監査で外部監査人に示されている。監査報告書には「一九年度のしゅん工をめどに大規模改修工事の計画を策定している」と書かれており、インターネットで公表されている。
市は当面、緊急性のあるトイレなどの小規模な修繕をする予定だが、収蔵庫や空調は先送りになった。
収蔵庫の拡張延期について、文化振興課は「容量がオーバーすることはないと思うが、収納の仕方などを工夫してもらうしかない」としているが、美術館関係者からは「収蔵庫は既に満杯に近く、美術品の収集に影響が出る可能性がある」との声が出ている。(東京新聞 2016年3月19日)
車内での計測で7マイクロシーベルト近くを記録する国道6号線の厳しい環境 ~よこはま健康友の会での福島視察旅行 その三
帰り道は、原発横を走っている国道6号線を通りながら帰路につきました。
ハッキリ言って異常な状況です。
道々には、汚染土壌が入った思われる黒いフレコンバッグがあちらこちらにあります。

フレコンバッグに入れられた汚染土壌の持っていき場はなく、空き地があれば積み上げられています。

国道6号線は開通したといっても、車以外のものは通れません。バイクも自転車もダメです。
そして、右にも左にも曲がることは許されません。必ず、横道はガードされており、警備員もいます。

ずっとバスの車内で線量計を持って測っていましたが、最高で6.857マイクロシーベルトを記録しました。

まさにこういうことです。

こんなところを政府は開通させたわけです。何も事態は変わっていないのに・・・。
